中小企業のためのマイナンバー(2)
マイナンバーの罰則規定
マイナンバーに関する法律は、正式には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」ですが、長いので番号法と記載します。
昨年、大手企業が個人情報を流出して話題になり、今年の6月にも日本年金機構の個人情報の流出が話題になりました。報道の扱われ方からも、個人情報に対する関心の高さが伺われます。
番号法では、個人情報利用事務等に従事する者が、正当な理由無く、特定個人情報ファイルを提供した場合には、4年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又は、その併科と規定しています。企業で、従業員の不正による番号の漏洩があった場合には、企業イメージを毀損するだけでなく、懲役などの実刑判決にも繋がる可能性があります。
マイナンバーの取扱いに求められる安全管理措置
マイナンバーは、その制度の性格上、非常に取扱いを慎重に行う必要があります。税金や社会保険の手続のために、会社に入社した場合には、マイナンバーを会社に伝える必要がありますし、不動産を賃貸する場合や、源泉徴収の対象となる報酬を受け取る場合には、支払調書作成のために、支払いをする相手方に自分のマイナンバーを伝える必要があります。つまり、パスワードのように秘匿されるものではありませんが、法律の定めがある場合には伝えることが必要な番号です。一方で、安全にマイナンバー制度が運営されるためには、なりすましなど悪意を持った者による犯罪に備えるため、マイナンバーを扱う者には、安全管理措置が要求されています。
安全管理措置の大まかな体系としては、下記のとおりとなります。
| ①組織的安全管理 | 事務取扱者及び責任者の明確化 |
| ②物理的安全管理 | 特定個人情報を取り扱う区域の管理等 |
| ③技術的安全管理 | 情報システムの管理等 |
| ④人的安全管理 | 事務取扱担当者の監督・教育 |
詳しい説明は、各論の話しとなるので、次回以降とします。簡単に説明すると、①会社としての仕組み作り、②マイナンバーを取り扱う場所や保管方法について、③パソコン等による管理を行う場合のルール、④マイナンバーを取り扱う者の教育と監督について、マイナンバーが適切に管理できるようにしてくださいという内容です。
安全管理措置の中小規模事業者に対する特例
番号法では、重い罰則規定があり、安全管理措置についても細かな定めを置いています。ただし、中小企業に、大企業と同じルールを適用することは、現実的ではありません。そこで、安全管理措置については、中小事業者に対する特例を設けることで実務への配慮がされています。
番号法における中小企業とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者で、次に掲げる事業者を除く事業者をいいます。
|
マイナンバーに関して、中小事業者に該当する場合は、安全管理措置に関する取扱いが緩和されています。まずは、自分の会社が中小事業者に該当するのか否かの確認が必要です。従業員が100人以下でも、税理士事務所、社会保険労務士事務所、健康保険組合、信用金庫、信用組合などは、中小事業者から除かれることになります。
なお、保険の代理店等が中小事業者に含まれるかは、微妙なところですが、保険会社で、代理店がマイナンバーを取り扱わない仕組みを模索しているとの話しを聞いたことがあります。
自分の会社が中小事業者から除かれる業種でないか否かについても注意が必要です。
次回は、安全管理措置について、原則的な取扱いと中小事業者向けの取扱いを比較してご紹介していきます。
マイナンバーの概要
マイナンバーは、市区町村長が住民票を有する全ての者に対して指定する12桁の番号です。マイナンバーの通知は、今年の10月から始まり、市区町村から通知カードが郵送されてきます。
マイナンバーは、住民票を有する全ての者に対して付与されるものであり、成人に限らず、赤ん坊にも割り振られることになります。実際に、確定申告、年末調整、社会保険の手続などの際に、扶養家族のマイナンバーを記入することになります。
なお、マイナンバーは、原則として変更されません。しかし、漏洩などがあり、不正に使われるおそれがある場合に限り、本人の請求や市区町村の職権によって変更されることになります。
また、マイナンバーは住民票を有する者に指定されるため、日本人でも海外に長く住んでいて、住民票を有しない場合には、マイナンバーが付されません。一方で、外国籍の方でも住民票がある長期の滞在者や特別永住者などにはマイナンバーが指定されることになります。
マイナンバーの利用の制限
レンタルビデオ店などの会員になる際に、免許証のナンバーを書き写されること、あるいは、携帯電話を契約するにあたって免許証のコピーを取られることなどがあります。免許証が身分証明書の一つとして、民間企業で利用されている一例です。
一生変更されることがないマイナンバーは、個人を特定して管理するには非常に便利に思えますが、民間企業でマイナンバーを利用することは認められていません。
マイナンバーの利用が認められるのは、国や地方公共団体が、社会保障、税、災害対策の3つの分野で、さらに法律か条令で定められた手続でしか利用できないことになっています。
マイナンバーを大切にしなければならない理由
会社に入社する場合に、社会保険の手続、扶養控除等申告書など、本人だけでなく家族のマイナンバーを記載することになります。また、学生時代にアルバイトを、10箇所で行えば、10箇所の会社に対してマイナンバーを提出することになります。あるいは、不動産のオーナーは、借り主に対して借り主が変更になる度に、支払調書に記載するためにマイナンバーの提出を求められる場合があります。
一方で、マイナンバーは大切な番号なので、むやみに他人に提供することはできませんと一般的に説明されています。
マイナンバー関係の研修会の際に、むやみに他人に教えてはならないのに、会社に提供しなければならないのは、矛盾しているのではないかという質問を受けることがあります。この点については、マイナンバー自体は、暗証番号とは異なり、秘匿する番号ではなく、必要に応じて提供する番号と理解してくださいと説明しています。
民間企業が、税務署への支払調書の作成、年末調整及び社会保険の手続で、従業員のマイナンバーを提供してもらう必要があります。その場合でも、マイナンバーを従業員コードとして利用するなど、民間企業内での利用はできないことになっています。あくまでも、国や地方公共団体に対する手続を行うときのみに利用するということになります。
マイナンバーが漏洩した場合に、必ずしも大きな被害に結び付くというわけでは、ありません。しかし、悪意を持った者が他人のマイナンバーを入手することで、「なりすまし」などの犯罪に繋がる可能性も考えられます。つまり、暗証番号のように秘匿すべき番号ではないものの、マイナンバーの制度を守るためには、大切に扱わなければならない番号と位置付ける必要があります。
中小企業でも、従業員や家賃の支払先などのマイナンバーを入手する必要が生じます。民間企業が、他人から預かるマイナンバーをどのように管理していく必要があるのかについて、次回以降ご説明していきます。
通常は翌月10日が納期限
従業員に給与を支払う際に、源泉所得税、復興特別所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険と多くの項目について、天引きすることになります。
源泉所得税と復興所得税を給料から天引きする場合に、源泉徴収という言葉を用います。源泉徴収した、源泉所得税等は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付が必要になります。
個人住民税についても、事業主は特別徴収義務者として、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収しなければならないこととなっており、給与から住民税を天引きする取扱いとなっています。そして、源泉所得税等と同様に翌月10日までに納付しなければなりません。
なお、源泉所得税等の場合も住民税の場合も、翌月10日が土曜日、日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日が納期限となります。
納期限の特例について
源泉所得税等の場合でも住民税の場合でも、毎月、納付を行うことは、中小企業にとっては煩雑となります。そこで、半年分まとめて納付する納期の特例という取扱いがあります。源泉所得税等の場合でも住民税の場合でも、納期の特例を利用したい場合は、届出が必要になります。要件は、源泉所得税等及び住民税のいずれも、給与の支給人員が常時9人以下であることです。
なお、源泉所得税等については、その年の1月から6月までに源泉徴収した源泉所得税等は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した源泉所得税等は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
一方で、住民税の納期限は、6月分から11月分までが12月10日、12月分から翌年5月分までが翌年6月10日となっており、源泉所得税等の納期限と一か月ずれることになります。
なお、納期の特例を利用する場合に、金融機関に行く回数は減少しますが、金額がまとまってしまうケースがありますので、資金繰りの計画に含めておくことが重要です。
源泉所得税等の納付と住民税の特別徴収に関する実務上の注意点
源泉所得税等で、注意しなければいけないのは、不納付加算税の取扱いです。納期限までに支払いが間に合わなかった場合に、遅れた期間に応じて延滞税が発生しますが、延滞税は日割り計算されるために早い段階で気づけばそれほど大きな金額となりません。一方で、不納付加算税は、1日遅れただけでも5%の負担が生じてしまいます。仮に、納付すべき源泉税額が100万円の場合は、1日遅れただけで5万円の加算税が生じる可能性があります。不納付加算税が5%となるのは、自発的な納付で、かつ、税務調査による告知があることを予知した場合でないことが要件とされており、税務調査で発覚した場合などは10%の不納付加算税となり、さらに重い負担となります。
なお、その直前1年間で納付が遅れたことがない源泉徴収義務者、初めて源泉徴収義務者となった場合で最初の納付の際に、納期限までに納付ができなかった場合で、期限後一か月以内に自主的に納付すれば、不納付加算税が課税されない取扱いがあります。
特別徴収した住民税については、納期限を遅れると延滞金が課税される仕組みになっています。
また、住民税については、源泉所得税等のように当月の給与の額によって金額が変動するわけではなく、前年の所得に基づいて、従業員の居住する市区町村から届く通知書に基づいて納付することになります。従業員が退職した場合などは、事由発生日の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。この際に、通知書と同時に送付されてきた納付書に印字されている金額には退職者分も含んでいるので、退職者分を控除した金額に修正して納付することが必要になります。退職者分の住民税を、誤って納付し続けるというミスがありがちですので、お気をつけください。
秋には制度案を取りまとめる方向?
税制改正大綱によれば、消費税の軽減税率制度については、平成29年度からの導入を目指すとされています。本当に平成29年度からの実施を行うためには、平成27年の秋には制度案を取りまとめ、平成28年度税制改正に間に合わせる必要が生じます。
先月22日と27日に、与党税制協議会・消費税軽減税率制度検討委員会の会合が行われるなど着々と準備が進んでいるように見えました。ところが、6月10日になって、与党協議が行き詰まり、当面の間、開催を見送ると報道されました。
昨年、与党税制協議会から報告書が公表され、こちらの税務関連情報でも、ご紹介しましたが、その時は、あらゆる可能性を紹介するというような漠然としたものでした。
先月の会合の内容は、軽減税率の対象を「酒類を除く飲食料品」、「生鮮食品」、「精米」に絞って、どのような影響があるかが検討されており、より現実的な話題となっています。
5月に議論された内容
この5月に議論された内容は、軽減税率の対象を3案に絞り込んでのものでしたが、論点をまとめると以下のようになります。
| 対象品 | 経理方法 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|
| 酒類を除く飲食料品 | インボイス方式 ただし3年程度は経過措置として請求書等を保存する方式 | 消費者の理解が得やすい | 財源に与える影響が大きい |
| 生鮮品 | インボイス方式 ただし3年程度は経過措置として請求書等を保存する方式 | 同上 | 同上 |
| 精米 | 区分経理に対応した請求書等を保存する方式 | 財源に与える影響が小さい | 消費者の理解が得にくい |
軽減税率の対象を、酒類を除く飲食料品とすれば、消費者の理解は得られやすいものの、財源に与える影響は大きく、何らかの形で代替財源が必要となります。
軽減税率の対象を精米に限定すれば、財源に与える影響は少なく、インボイス方式を必ずしも必要としないのであれば実行可能性は高いかもしれません。一方で、消費者の理解を得られるのか否かで疑問が残ります。
生鮮食品を軽減税率の対象とする場合は、両者の長所短所について折衷的な結果となります。しかし、生鮮食品より価格が安いとされる加工食品が一般税率、生鮮食品が軽減税率となるのは、逆進性で問題があるとの指摘もあります。また、生鮮食品の線引きなども、現実的には難しそうです。
軽減税率の対象を精米のみとする場合以外は、インボイス方式の導入が不可欠とする方向のようです。インボイスとは法定記載事項が記載されている請求書のようなものと考えてください。3年程度は猶予期間を設けるようですが、インボイスを発行するためのシステムを導入する必要があるなど、インボイスの発行が必要な事業者にとっては負担が生じることに繋がります。
軽減税率の行方を予想すると
大綱では、平成29年度からの導入を目指すとしていましたが、現状の雰囲気では、時間切れもあり得るのかもしれません。与党協議がまとまらなければ、結果として先送りとなる可能性があります。
結局のところ、軽減税率を導入して不足する財源をどこから捻出するのか、言い方を変えれば、一般消費税率を引き上げる前提の話しができなければ、軽減税率の話しは先に進まないのかもしれません。消費税率10%への引き上げも先送りしている現状では、触れることが難しい話題で、先送りせざるを得ないのかもしれません。
通達の改正
平成27年3月10日の馬券の払戻金に対する最高裁判決を受けて、その数日後に、国税庁は「最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について」という文書を公表し、通達を変更することを明らかにしていました。
平成27年5月に変更後の通達が公表されたので、ご紹介します。
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
(一時所得の例示) 34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(注)
※ 以下は変更がないので省略 | (一時所得の例示) 34-1 次に掲げるようなものに係る初頭は、一時所得に該当する。
※ 以下は変更がないので省略 |
通達の内容は、括弧書きと注意書きが追加される形で、基本的なスタンスには変化がありません。
注意書きの内容は、①馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいて、②インターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に、③個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして、④当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げていることを要件として、さらに結果として、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合としており、一時所得とならないケースは、かなり限定的な取扱いとみるべきです。
一方で納税者が負けている判決も
最高裁判決では納税者が勝訴しましたが、平成27年5月14日の東京地裁判決では、納税者が敗訴しています。金額的には最高裁判決と同等かそれ以上だったそうですが、馬券の購入の仕方が「男性の馬券購入は一般的な愛好家と変わらない」として、請求を棄却したそうです。
通達の規定ぶりからも、一時所得にならないケースの方が希であり、実務的には、難しい判断の局面が増えたようなイメージもあります。
通達変更の影響
通達の改正は、今後の取扱いに影響すると同時に過去の取扱いにも影響があります。法律の変更はなく、通達が法律の解釈と異なっていたわけですから、過去に通達にしたがった処理をしていた場合に、更正の請求を行うことが可能です。
具体的には、今回の通達改正を知った日の翌日から2か月以内に更正の請求をすれば、最大で5年分の納め過ぎた税金について還付を受けることが可能です。知った日から2か月以内ですから、心当たりがある場合には、慌ただしい手続となります。
住宅ローン減税の基本的な要件
住宅ローン減税の適用を受けるための要件として、基本的なものとしては、下記の通りです。
- 借入金の償還期間又は割賦期間が10年以上であること
- 対象となる借入金は、居住用の住宅、敷地、増改築資金であること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 合計所得金額が3000万円以下であること
なお、中古住宅の場合は、築年数が木造の場合は20年以内であること、耐火構造の場合は25年以内であること、耐震基準であることの証明、瑕疵担保保険に加入していることなどの条件が加わります。
また、借入金が勤務先の社内貸付制度を利用している場合は、年利率が1%以上であることが必要となります。
平成25年以前に居住開始した場合の住宅ローン減税
(1) 一般の住宅の場合
平成25年以前の住宅ローン減税の概要は、以下のとおりです。政策的な減税であるため年度によって、大きく有利不利があります。改正時点では、景気の早期回復を趣旨として、早く購入する方が、有利な制度が適用できる仕組みとなっていました。
| 居住した年 | 控除期間 | 借入金の残高の 限度額 | 控除率 | 年間の控除 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年 | 10年又は15年 | 2,000万円 | 0.4~1% | 8~20万円 |
| 平成21年 | 10年 | 5,000万円 | 1% | 50万円 |
| 平成22,23年 | 4,000万円 | 40万円 | ||
| 平成24年 | 3,000万円 | 30万円 | ||
| 平成25年 | 2,000万円 | 20万円 |
(2) 認定長期優良住宅等に該当する場合
なお、平成21年から平成23年までに居住開始した住宅が、認定長期優良住宅に該当する場合は、下記のとおり、認定長期優良住宅に該当しない住宅を取得した場合に比べて有利な取扱いとなります。
| 居住した年 | 控除期間 | 借入金の残高の 限度額 | 控除率 | 年間の控除 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21~23年 | 10年 | 5,000万円 | 1.2% | 60万円 |
平成24年以降の居住開始からは、認定長期優良住宅に加えて、認定低炭素住宅に該当する場合にも、優遇措置がとられ下記のような取扱いとなっています。
| 居住した年 | 控除期間 | 借入金の残高の 限度額 | 控除率 | 年間の控除 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年 | 10年 | 4,000万円 | 1% | 40万円 |
| 平成25年 | 3,000万円 | 30万円 |
平成26年以降の住宅を取得した場合の住宅ローン減税
消費税率の引上げに備えて、平成25年度税制改正で改正が行われました。消費税率引上げ後の税率で住宅を取得した場合には、より大きな住宅ローン減税の適用を受けられる制度で、駆け込み需要とその反動を抑制しようとする趣旨です。
平成27年度税制改正では、消費税率10%への引上げが延期されたことに伴い、住宅ローン減税の適用期間について改正されました。
消費税率については、経過措置の適用で、消費税率引上げ後も旧税率が適用される場合があるので、その時点における引上げ後の税率で取得した場合を、特定取得として、旧税率で取得した場合と区別して住宅ローン減税を適用します。
(1) 一般住宅の場合
| 取得形態 | 居住年月日 | 控除期間 | 借入金の残高の 限度額 | 控除率 | 年間の控除 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特例取得以外 | 平成26年~ 平成30年6月 | 10年 | 2,000万円 | 1% | 20万円 |
| 特定取得 | 4,000万円 | 40万円 |
(2) 認定長期優良住宅等に該当する場合
| 取得形態 | 居住年月日 | 控除期間 | 借入金の残高の 限度額 | 控除率 | 年間の控除 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定取得以外 | 平成26年~ 平成30年 | 10年 | 3,000万円 | 1% | 30万円 |
| 特定取得 | 5,000万円 | 50万円 |
NISAの非課税枠の拡大
平成26年1月1日より利用が可能となったNISA制度では、年間100万円を限度とする上場株式等の購入であれば、その株式等による配当や売却益が非課税とされます。
平成27年度税制改正で、上記NISAの非課税枠が、年間の購入額100万円から年間の購入額120万円へと拡大されることになりました。なお、非課税枠の拡大は、平成28年分からとなります。
金額が100万円から120万円となったのは、月々10万円ずつ積立的な投資を行いやすくする趣旨です。
なお、NISAについては複数の口座を持つことができないように、口座開設時の手続が煩雑であるとの問題点が指摘されています。この点については、マイナンバーの利用により、口座開設が簡素化されることも予定されています。
ジュニアNISA制度
従来のNISA制度は、その年の1月1日において満20歳以上である者に利用者が限定されていました。平成27年度税制改正で、その年の1月1日に20歳未満であっても、利用可能なNISA制度を設けました。極端な場合、生まれたばかりの子どもに、NISA口座を持たせることもできます。なお、年間の購入額が80万円であるなど、従来のNISAとは非課税限度額が異なるためジュニアNISAという呼び方をして区別することが一般的です。
従来のNISAとジュニアNISAの異なる点は、下記の通りです。
|
通常は、未成年者は投資する資金を有しないので、資金の拠出については親権者等が行い、贈与税の非課税限度額の枠を利用して、毎年継続して投資が行えることが想定されています。
また、18歳までは、払出し制限が設けられることになります。ジュニアNISAの株式を売却した場合等は、課税未成年者口座へ移動されることになり、通常は払出しができません。ただし、火災など災害等の事由があった場合は、税務署長の確認を受けることで払出しが可能となります。
帰ってくる予定がある場合は?
さて、海外へ出国する場合に、保有する有価証券などについて、時価で売却したものとみなして、課税されるのが出国時課税制度です。ここで、疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますが、出国はするけれども、数年後には戻ってくるという場合は、どうなるのでしょうか。日本に戻ってくるまでの間、有価証券を持ち続けているような場合にまで、課税されるのでは困ってしまいます。
出国時課税制度の適用を受けた者が、国外転出の日から5年以内に帰国した場合で、国外転出の際に有していた有価証券等を引き続き保有している場合には、出国時課税制度による課税を取り消すことができる仕組みとなっています。この場合は、自動的に税金が戻ってくるわけではなく、帰国の日から4か月以内に更正の請求を行うことが必要となります。
なお、帰国した場合でも、国外転出の際に有していた有価証券を売却した場合には、売却した部分について課税が取り消されることはありません。
帰国予定の場合の納税猶予制度
帰国した場合に更正の請求ができるとしても、出国時に売却していない有価証券について課税される仕組であるため、保有資産の大部分が有価証券である場合は、納税資金が不足するという事態が生じる可能性があります。
出国時課税制度の適用を受けた者が、国外転出の日の属する確定申告書に納税猶予を受ける旨の記載をすることで、国外転出をした日から5年を経過する日まで、納税猶予を選択することが可能です。なお、5年以内に帰国する場合は、帰国の日から4か月を経過する日までが納税猶予期間となります。
なお、納税猶予制度を受けるためには、納税猶予額及び利子税に相当する担保を提供することと、納税管理人の届出が必要となっています。
また、事情により海外出張が5年を超えるようなケースも想定されるので、納税猶予の期間については、申請をすることで、国外転出の日から10年を経過する日まで延長できることになっています。
国外転出とは?
さて、国外転出とは、どのような内容を示すのでしょうか。当然、海外旅行などで、短期間の間、海外に行く場合には含まれないことになります。
本制度については、国税庁よりFAQが公表されていて、詳細は下記をご覧頂ければと思います。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/02.pdf
上記FAQの中で、国外転出について、「国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。」と条文通りの説明があります。一般的には、住所地の市区町村に対して、国外転出届を提出することで国外転出となります。
ただし、所得税法基本通達では、住所について、生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的な事実により判定するとしています。つまり、実質的な判断が行われるので、国外転出届出を提出しなければ課税されないというわけではありません。
出国時課税制度が必要になった理由
租税条約では、株式など有価証券の売却益については、有価証券を売却した者が居住している国に課税権があるとされています。しかし、シンガポールや香港などでは、有価証券の売却による利益については非課税とすることで、世界中から富裕層が移住しやすいような政策をとっています。
多額の含み益のある有価証券を保有している日本人が、国内でその含み益のある有価証券を売却した場合には、多額の税金がかかることが予測できます。この場合に、シンガポールへ移住してから、含み益のある有価証券を売却することで、有価証券の売却益に対する課税を逃れることが可能となっています。このような、国際的な租税回避を防止することを趣旨として、平成27年度税制改正で導入されました。
制度の概要
国外転出をする居住者が、有価証券などを有する場合に、その国外転出の時に、その有価証券などを売却したものとして、所得税の課税が行われることになります。
なお、具体的な計算方法については、納税管理人がいる場合といない場合では、以下のとおり異なる内容になります。
(1) 納税管理人がいる場合
| 国外転出時の有価証券等の時価 - 有価証券等の取得費 = みなし譲渡所得 |
(2) 納税管理人を定めない場合
| 国外転出予定の3ヶ月前の日における有価証券の時価 - 有価証券の取得費 = みなし譲渡所得 |
この相違は、納税管理人を定めない場合は、出国時までに確定申告をする必要があることから、国外転出の予定日の3月前の時価を用いることになっているためです。
なお、有価証券だけではなく、未決済デリバティブ取引についても、決済をしたものとみなした利益について、課税される仕組みになっています。
なお、本制度は平成27年7月1日以降から適用開始となります。
出国時課税制度の適用対象者
出国時課税制度は、富裕層の国外転出による国際的な租税回避を防止することを目的としており、対象となるのは下記の要件を満たす場合です。
(1) 資産規模要件
| 国外転出時の有価証券の時価と未決済デリバティブ取引等の利益の額又は損失の額が1億円以上である者(納税管理人を定めない場合は国外転出予定日の3ヶ月前の時価で判定) |
(2) 在住期間要件
|
贈与、相続があった場合の取扱い
なお、上記の適用対象者が、有価証券等を贈与、相続、遺贈により非居住者に移転した場合は、適用対象者が国外に転出してから、贈与、相続、遺贈した場合と同様の結果になるので、贈与、相続、遺贈があったときにも時価で売却したものと、みなして課税される仕組みとなっています。
贈与、相続の場合も平成27年7月1日以降から適用されることになっており、駆け込みで6月までに贈与を行うなどの対策が行われているようです。
ふるさと納税の魅力
ふるさと納税自体は平成20年度税制改正で導入されましたが、ここ数年の税制改正の中で、もっとも注目された制度かもしれません。とにかく、大人気の制度と言っても過言ではないでしょう。
例えば、控除限度額に余裕がある場合なら、5万円の寄付をした場合、4万8千円は、所得税や住民税が減額され、実質の負担としては2000円となります。一方で、自治体によっては、寄付金に対して、返礼品を贈ってきてくれるという取扱いを行っています。寄付金額に対する、返礼品の値段を還元率と呼びますが、還元率で50%以上としている自治体が相当多くあります。つまり、5万円の寄付をした場合に、実質負担は2千円なのに、還元率50%なら、2万5千円の返礼品が贈られてくることになります。2千円で、2万5千円の品物が入手できるわけですから、どう考えてもお得な制度です。
なお、返礼品としては、自治体の地域の特産品である肉、山の幸、海の幸、米などの他、パソコンを用意している自治体もあり、非常に多彩な内容です。「ふるさと納税」と「特産品」などのキーワードで検索すると、気に入る返礼品がみつかるかもしれません。
控除限度額に注意
ふるさと納税で注意が必要なのは、税額控除に限度額が設けられていることです。
従来は、個人住民税の所得割の1割が上限とされていましたが、平成27年度税制改正で、平成28年度分以後の個人住民税については、個人住民税の所得割の2割が上限となりました。住民税は、平成27年度の所得に基づいて、平成28年度分の税額が決定される仕組みとなっており、平成27年に行った寄付金から、従来の倍の控除限度額という取扱いになります。
なお、課税所得金額に応じて、いくらの金額の寄付までが、有利になるのかについて、示すと下記の通りです。
| 課税所得金額 | 寄付金の目安 | 課税所得金額 | 寄付金の目安 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 5万円 | 800万円 | 24万円 |
| 300万円 | 7万円 | 1000万円 | 35万円 |
| 400万円 | 11万円 | 1200万円 | 42万円 |
| 600万円 | 17万円 | 1500万円 | 53万円 |
総務省のサイトでは、収入金額と家族構成に応じた一覧表を公表しているので、参考にしてください。
参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf
また、住宅ローン減税を受けている場合などは、税額控除額が別途あるため、計算結果が変わってくるので注意が必要です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度により確定申告不要に
ふるさと納税を促進し、地方創世を推進するために、確定申告が不要となる、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。サラリーマンなどがふるさと納税を行った場合は、何の手続きもしなくてもふるさと納税の額にみあった税額控除が受けられる便利な制度です。
具体的には、寄付を行う際に、自分の住所地に控除申請をしてくれるように依頼すると、寄付を行った自治体が、住所地の自治体に必要事項を通知する仕組みとなっています。
ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月以降の寄付からの取扱いなので、平成27年3月までに寄付をしている場合には、確定申告が必要になります。また、寄付先が5つを超えるような場合は、確定申告が必要となります。
◆制度の概要
平成25年4月1日から施行されている教育資金の一括贈与制度は、非常に注目度も高く、信託による利用の契約件数のみでも10万件以上となっており、納税者のニーズにマッチした制度でした。そこで、平成27年度税制改正では、結婚・子育て資金の一括贈与制度を新たに創設しました。
扶養義務者間であれば、生活費については、その都度贈与が行われ、その支払いに直接充てられている場合は、非課税とされています。教育資金、結婚・子育て資金についても、必要の都度、贈与されている分には非課税となるものを、必要の都度ではなく、一括して贈与しても非課税とする点が両制度の共通点です。
なお、利用にあたっては、教育資金の一括贈与制度と同様に、直系尊属が金銭を拠出し、信託銀行などの金融機関に信託等を行うことが条件となります。
金額については、受贈者1人につき1,000万円までとされており、平成27年4月1日から平成31年3月31日までに拠出されたものに限り、贈与税を課税しないという仕組みです。なお、1,000万円のうち、結婚資金として利用できるのは300万円までに限定されています。
◆具体的な資金の使途
結婚・子育て資金の具体的な使い途としては、下記のような内容です。
結婚に際して支出する婚礼(結婚披露宴を含む。)に要する費用、
住居に要する費用及び引越に要する費用など
(2)子育て費用
妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のものなど
子育て費用について、不妊治療やベビーシッターにかかる費用なども含まれます。
◆教育資金の一括贈与制度との相違点
金額の上限が、教育資金は1,500万円、結婚・子育て資金は1,000万円と、金額の違いこそありますが、仕組みとしては非常に似ています。しかし、決定的に違う点があります。
教育資金の一括贈与制度は、贈与した者が死亡した場合に、相続財産に組み込まれることはなく、受贈者が30歳になった時点で未使用の金額があれば、その残額について贈与税が課税される仕組みとなっています。相続財産に組み込まれないという点では、短期的な相続対策としての効果があるという特徴があります。
一方で、結婚・子育て資金については、贈与をした者が死亡した場合は、相続財産に組み込まれる仕組みになっています。孫への相続の場合のような2割加算の対象とならないので、まったくメリットがないわけではありませんが、相続対策としての効果は薄いと考えるべきです。なお、贈与をしたものが生存している場合には、結婚・子育て資金は受贈者が50歳になって、未使用の金額があれば、その残額について贈与税が課税される仕組みとなっています。
◆教育資金の一括贈与制度の改正点
教育資金の一括贈与制度は、平成27年12月31日で終了する予定でしたが、平成27年度税制改正で、平成31年3月31日の拠出まで、期限が延長されました。
また、教育資金の中に、留学の渡航費用と通勤定期券代が含まれることになりました。なお、留学中の生活費については、教育資金に含まれないことになっていますが、扶養義務者が生活費としてその都度送金することにより、結果として贈与税は課税されないことになります。
従来の事業承継税制
事業承継税制は、平成21年度税制改正により創設されました。ところが、創設当初の取扱いでは、①一定の雇用を維持できなかった場合に納税猶予が打ち切りとなること、②納税猶予が打ち切りとなった場合に多額の利子税の負担が生じること、③親族間承継しか認めないという制約があったこと、④事前の確認が必要とされ、事後の手続も煩雑であったこと、⑤先代経営者の退任が条件とされていたことなど、使いにくさの目立つ制度でした。
利用しにくいという指摘を受けて、平成25年度税制改正により、問題点として指摘されていた部分の多くについては、改善され、使い勝手がよくなってきました。この点については、下記をご参照ください。
http://www.tohoren.or.jp/zenkoku/index.asp?patten_cd=12&page_no=563
平成27年度税制改正による改正点
平成27年度税制改正における事業承継税制の変更点として、注目度が高いのは、贈与税の納税猶予に関する取扱いです。
相続税について納税猶予制度を利用していた場合に、保有している株式を、さらに、後継者に事業承継税制を利用して生前贈与する場合は、納税猶予されていた相続税額は免除されるという取扱いでした。
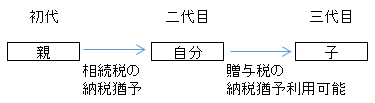
一方で、先代経営者より贈与税の納税猶予制度を利用して、株式を取得した経営者が、先代経営者が存命中に、その株式を次の後継者に対して贈与する場合に、納税猶予が打ち切られてしまい、納税猶予されていた贈与税について納税が必要な仕組みでした。
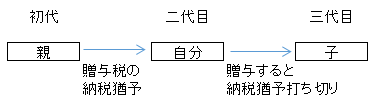
このような取扱いにしたのは、親から自分への相続税について、世代飛ばしを、認めない趣旨だったと思われます。ところが、高齢化が進むことにより、親が95歳、自分が65歳というような状況で、子に事業承継税制が利用できないというのでは、酷な話しです。
そこで、平成27年度税制改正により、初代から贈与税の納税猶予を受けていた二代目経営者が、さらに三代目へ贈与税の納税猶予をした場合に、二代目経営者の猶予税額について免除するという取扱いにしました。
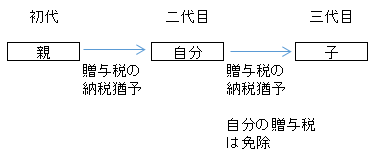
なお、この場合の納税猶予の免除は、最初の贈与税の納税猶予制度の贈与税の申告期限の翌日から5年間経過した後に行われる贈与に限定されます。
また、今回の改正で、最初の相続税・贈与税の納税猶予制度の相続税・贈与税の申告期限の翌日から5年以内の贈与でも、身体障害等のやむを得ない理由により、次の後継者に贈与税の納税猶予制度を利用する場合には、猶予税額の免除が認められることになりました。
国外事業者による電気通信役務に対する課税の仕組み
電気通信役務について、役務の提供を受ける者の住所で内外判定を行うとした場合に、海外で役務提供を行っている者から課税できるのかという現実的な問題があります。そこで、今回の改正では、実体に即して2つの課税方法を用意して対応しています。
(1)リバースチャージ方式
国外事業者が行う電気通信役務の提供のうち、その役務の性質又はその役務の提供に係る契約条件等により、役務の提供を受ける者が事業者であるものが明らかなものを「事業者向けの電気通信役務の提供」と分類します。そして、事業者向けの電気通信役務の提供については、役務の提供を受ける者が消費税の納税義務を行うことになります。
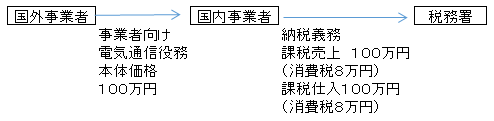
リバースチャージ方式の課税対象となるのは、事業として他の者から受けた事業者向け電気通信役務の提供で、「特定仕入」と呼ばれます。リバースチャージ方式の納税義務の対象は国内において行った課税仕入のうち「特定仕入」に該当するもので、「特定課税仕入」と呼ばれます。実務のイメージで言えば、グーグルに支払う広告費などが該当します。
課税仕入を行った者が、納税義務を負うという点に違和感がありますが、実際には上記の図のように8万円の消費税を預かり、8万円の消費税を支払うということで、納税額はゼロとなるケースが多いはずです。別の言い方をすれば、100万円について課税仕入ができなかった従来と結果は同じとなります。そこで、当面の間は、課税売上割合が95%以上の場合は、その課税期間において行った特定課税仕入はなかったものとして取り扱われます。一方で課税売上割合が95%未満の場合には、納税額が生じますので注意が必要です。
また、中小事業者向けの取扱いとして、免税事業者はリバースチャージについても納税義務は生じません。簡易課税の適用を受ける事業者についても、当面の間は、特定課税仕入はなかったものとして扱われるとしており、従来と変化はありません。
(2)国外事業者申告納税方式
国外事業者が行う電気通信役務の提供のうち「事業者向け電気通信役務の提供」以外のものを「消費者向け電気通信役務の提供」と呼びます。「消費者向け電気通信役務の提供」については、役務提供を行っている国外事業者が納税義務者となります。イメージとすれば、アマゾンによる電子書籍の販売などを想定していただけると馴染みやすいと思います。
ただ、ここで、国外事業者に納税義務を課すとしても、外国にいる事業者に強制力を行使できるのかという問題が生じます。仮に国内事業者が、外国事業者から「消費者向け電気通信役務の提供」を受けた場合に仕入税額控除を認め、一方で、国外事業者が消費税の申告を行わなければ、国として持ち出しが生じてしまいます。そこで、当分の間は、国内事業者が国外事業者から提供を受けた「消費者向け電気通信役務の提供」については、仕入税額控除の適用を認めないことにしました。つまり、従来通り、課税仕入に含まれないという、奇妙な状態になります。
しかし、国外事業者が、日本の消費税を納税している場合にまで、仕入税額控除を認めないのでは、消費税の仕組みとして問題となるので、「登録国外事業者」から受けた「消費者向け電気通信役務の提供」については、登録国外事業者の登録番号が記載された請求書等の保存を要件に仕入税額控除を認める取扱いとしています。
登録外国事業者とは、国内に税務代理人又は納税管理人又は事業所があるなどの要件を満たす一定の国外事業者であり、平成27年7月1日以降に、納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に申請書を提出することで、登録を受けることが可能となります。
国外事業者による芸能・スポーツ等の役務提供
外国人の芸能人、スポーツ選手等の個人事業者が、日本国内で仕事を行えば日本の消費税が課税されます。この場合に、基準期間の課税売上高によって納税義務の判定を行うのですが、課税庁としては非居住者の状況を把握しきれないため、適正な課税が行えないことについて、会計検査院により指摘されていました。
そこで、平成28年4月1日以後に行われる、国外事業者が国内において行う芸能・スポーツ等の役務の提供については、その取引に係る消費税の納税義務者が、役務の提供を行う事業者から役務の提供を受ける事業者に転嫁する仕組み、上記で説明しているのと同様に、リバースチャージ方式が採用されることになりました。
従来の取扱いと問題点
日本の消費税の課税対象となるものは、「国内において事業者が行った資産の譲渡等」とされており、国外で行われた取引、事業者でない個人が資産を売却した場合などは、消費税が課税されない仕組みとなっています。
消費税法が公布されたのは昭和63年12月30日で、現在のようにインターネットを利用した国際間の取引などは行われていない時代でした。取引が国内で行われたか否かの判定を内外判定といいますが、国内及び国外にわたって行われる役務の提供についは、国内において行われたかどうかが明らかでないため、役務の提供を行う者の事務所の所在地で内外判定を行うという仕組みにしました。これは、明らかでないものについて、白か黒かをはっきりさせる必要があったために、そのように決めたと考えればわかりやすいでしょう。
ところが、最近はインターネットを通じた、電子書籍、音楽、広告の配信などの電気通信役務の提供が一般的になりました。この場合に、国内の事業者が提供するものについては消費税が課税され、国外事業者が海外から行う役務提供については国外取引として消費税の対象外として扱われてきました。同じ種類の役務提供について、国内事業者が提供するか、国外事業者が提供するかで、税負担に差異が生じ、ひいては、国内・国外事業者における競争条件の不均衡が生じた状態となっていました。
そこで、平成27年度税制改正により、この取扱いを変更して、平成27年10月1日から適用することとしました。実務にも、かなり大きなインパクトを与える改正です。
内外判定基準の見直し
今回の改正で内外判定の基準が見直されることになりましたが、全面的に変更があるわけではなく、一部の取引についてのみ取扱いが変わります。例えば、役務の提供が行われた場所が明らかなものについては、従来通り役務の提供が行われた場所で内外判定を行います。また、役務の提供が行われた場所が明らかでないもので、国際運輸、国際通信、国際郵便、保険、プラント建設等に係る情報提供等については、従来通りで変更がありません。
今回の改正で変更があるのは、下記の内容に限定されています。
| 電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回路を介して行われる提供であって、電気通信役務の提供以外の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供や単に通信回線を利用させる役務の提供を除く |
このような役務の提供を「電気通信役務の提供」と定義して、従来は、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地で内外判定していたものを、役務の提供を受ける者の住所・居所又は本店・主たる事務所等の所在地で内外判定を行うように改正されます。
なお、役務の提供が行われた場所が明らかでないもので、上記の「電気通信役務の提供」に該当しない役務の提供については、従来通り、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地で判定することになります。
国外事業者が行う電気通信役務の提供については、国内取引と判定され、日本の消費税が課税されることになるのですが、その課税方式については、枝分かれして、少し難しい説明となるので、次回ご紹介させていただきます。
免税手続カウンター制度
外国人観光客が買い物をする場所として、秋葉原や銀座の映像がニュースなどに非常に多く登場します。秋葉原や銀座での映像が多いのは、なぜでしょうか。秋葉原や銀座には、輸出物品販売場が非常に多くあります。そして、輸出物品販売場で、外国人観光客が、一定の手続をして物品を購入すれば、消費税がかからないという取扱いを受けることができるのです。これは、消費税は、国内の消費に対して課税されるものであり、輸出物品については免税としていることとのバランスをとる取扱いです。外国人観光客が外国で利用するモノを日本で購入する場合に、輸出と同じ取扱いをするという趣旨です。
ただし、外国人観光客への販売であれば、全ての店舗で免税の取扱いができるということではありません。税務署へ輸出物品販売場として、許可を受ける必要があり、その許可を受けるための条件もハードルが高いものです。また、輸出物品販売場としての許可を受けることができたとしても、販売する際に、パスポートを確認して、購入記録表を作成、購入記録表をパスポートに貼り付け割り印、購入者誓約書にサインを受け取るなど事務手続が煩雑で、小規模な店舗では対応しにくいものでした。
平成27年度税制改正では、輸出物品販売場について、その販売場における全ての免税販売手続を、免税手続カウンターを設置する事業者に代理させることを前提とした許可制度となります。
他の事業者が経営する販売場における免税販売手続の代理をしようとする事業者は、その販売場が所在する次に掲げる場所に設けた物的施設において免税販売手続を行うことについて、納税地を所轄する税務署長の許可を受けなければなりません。
(イ)その販売場が商店街振興組合の組合員が経営する販売場であるときは、その組合の定款に定められて地区 (ロ)その販売場が中小企業等協同組合法上の組合の組合員が経営する販売場であるときは、その組合員が形成する一の商店街 (ハ)その販売場が大規模小売店舗内であるときは、その大規模商売店舗の施設 (ニ)その販売場が一棟の建物内にあるとき(上記(ハ)に該当する場合を除く。)は、その建物 |
この改正により、負担が重い事務手続を、免税手続カウンターを設置する事業者に委託することが可能となり、小規模な店舗でも容易に輸出物品販売場としての許可を受けることが可能になります。外国人観光客が多数来るような観光地においては、ショッピングセンター内、あるいは商店街に、免税カウンターを設置することで、街全体の集客力を高めるなど大きなビジネスチャンスとして期待できます。
臨時販売場制度
外航クルーズ船が寄港する港湾の港湾施設内に場所及び期限を定めて臨時販売場を設置しようとする事業者(既に輸出物品販売場の許可を受けている事業者に限る。)が、あらかじめ臨時販売場を設置する見込みである港湾施設につき納税地を所轄する税務署長の許可を受けている場合は、その設置日の前日までに輸出物品販売場を設置する旨の届出書を税務署長に提出することで、その臨時販売場を輸出物品販売場とみなす制度が創設されます。
従来は臨時の輸出物品販売場という取扱いがなかったため、本来の輸出物品販売場と同様に場所ごとに許可を受ける必要があり重い負担でした。今回の改正で、負担が軽減され、臨時の輸出物品販売場を設けやすくなります。
復興支援
福島復興再生特別措置法の改正を前提に、帰還困難区域など一定の区域内に平成23 年3月11 日において事業所を有していた法人で同法の避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を受けたものが、積立期間内の日を含む各事業年度において、その実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する支出に充てるため、その実施計画に記載された投資予定額の2分の1相当額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、損金算入することができます。
この準備金は、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の適用を受ける場合にはその適用を受ける減価償却資産の特別償却実施額に相当する金額を取り崩すほか、その積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日を含む事業年度の翌事業年度から3年間でその2年を経過する日を含む事業年度終了の時における準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入することになります。
中小法人向けの施策
税制改正大綱によると、租税特別措置については、毎年度、期限が到来するものを中心に、廃止を含めてゼロベースで見直しを行うとしています。中小企業向けの施策で、租税特別措置法で定められているものもあるため、今後の見通しについては微妙ですが、平成27年度税制改正においては、法人税法本法の取扱いも租税特別措置法の取扱いも基本的に現状維持という方向です。
(1) 中小法人の軽減税率の特例
中小法人の所得の金額のうち年800 万円以下の部分に対する税率が本来19%であるところを、15%とする取扱いの適用期限を、2年延長し、平成29年3月31日までに開始する事業年度までとなります。
また、公益法人等又は協同組合等の軽減税率についても、同様の取扱いです。
(2) 繰越欠損金の控除限度額の取扱い
中小法人に該当する場合は、欠損金の繰越控除制度において、控除限度額はその年度の所得の金額とされる取扱いは存置されます。なお、この取扱いは、法人税法本法の規定であるため、いつまでとの期限については定められていません。
(3) 貸倒引当金の取扱い
中小法人に該当する場合は、貸倒引当金について、法定繰入率を利用することができる取扱いが、2年間延長され平成29年3月31日までに開始する事業年度までとなります。また、公益法人等又は協同組合等に認められる割増特例について同様の期間まで延長されます。
※ 中小法人の範囲
中小法人とは、普通法人のうち、資本金の額もしくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本金もしくは出資を有しないものとされています。ただし、次の法人は除かれています。
ア 大法人との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
大法人とは、資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人、相互会社及び外国相互会社、法人課税信託に係る受託法人をいいます。
イ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を、その全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において、いずれか一の法人とその普通法人との間に、そのいずれか一の法人による完全支配関係があるとこととなる場合は、その普通法人
ウ 相互会社
エ 法人課税信託に係る受託法人
なお、公益法人等又は協同組合等の他、人格のない社団等も法人税法の取扱い上は中小法人に該当します。
最近は、中小法人の判定も難しく読むのが億劫かもしれません。およその理解としては、資本金5億円以上である法人の100%子会社などに該当すると、中小法人に該当しないと考えておくとよいでしょう。気になる場合は念のため税理士に確認しましょう。
地方拠点強化税制
地域再生法の改正を前提に、以下のような措置が講じられます。新聞で、大手メーカーが地方に拠点を移すという報道がされており、地方でも期待が高まっています。建物について特別償却あるいは税額控除ができるので、金額的な影響も大きなものになります。
(1) 地方拠点建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設
青色申告法人で地域再生法の改正法の施行の日から平成30年3月31 日までの間に地域再生法の地方拠点強化実施計画について承認を受けたものが、その承認の日から2年以内に、実施計画に記載された建物及びその附属設備並びに構築物で、一定の規模以上のもの(一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000 万円以上(中小企業者は1,000 万円以上))の取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の15%(一定の場合は25%)の特別償却とその取得価額の2%(一定の場合は4%)の税額控除との選択適用ができる制度です。税額控除を選択した場合は、当期の法人税額の20%が上限とされます。
なお、平成29 年3月31 日までの間に地方拠点強化実施計画について承認を受けた法人が取得等をしたものについては、その特別償却とその取得価額の4%(一定の場合は7%)の税額控除との選択適用ができることとして、早い段階で動けば優遇される取扱いがあります。
地方税の計算では、特別償却については法人住民税及び事業税に、税額控除については中小企業者等に係る住民税について適用されます。
(2) 雇用促進税制の拡充
雇用促進税制については、下記の優遇措置が講じられ、従来の雇用促進税制の要件を満たしている場合には一人当たり10万円の上乗せ、従来の要件を満たしていない場合でも減額はされるものの税額控除が可能で、さらにその後の年度にも税額控除されるという内容です。地方での雇用拡大に大きな期待が寄せられています。
イ 青色申告法人で地域再生法の改正法の施行の日から平成30 年3月31 日までの間に地方拠点強化実施計画について承認を受けたものが、その承認の日から2年以内の日を含む事業年度において、実施計画に従って移転又は新増設をした特定施設である事業所における増加雇用者数(法人全体の増加雇用者数を上限)に次の場合の区分に応じ次の金額を乗じた金額の税額控除ができる措置を講じられます。
(イ)現行の適用要件を満たす場合 50 万円
(ロ)現行の適用要件のうち雇用者増加割合が10%以上であることとの要件以外の要件を満たす場合 20 万円
(注)上記イの措置の適用を受ける場合で上記イ(イ)に該当する場合には、現行の雇用促進税制の適用の基礎となる増加雇用者数から、この措置の適用の基礎となる増加雇用者数が控除されます。
ロ 青色申告法人で地域再生法の改正法の施行の日から平成30 年3月31 日までの間に地方拠点強化実施計画(その法人の特定施設の特定地域から大都市等以外の地域への移転に関するものに限る)について承認を受けたものが、その承認の日から2年以内の日を含む事業年度(以下「対象年度」という)において上記イの措置の適用を受ける場合には、対象年度のうちその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(その特定施設である事業所における雇用者数又は法人全体の雇用者数が減少した事業年度以後の事業年度を除く)において、対象年度のうち当該事業年度以前の各事業年度のその特定施設である事業所における増加雇用者数の合計数に30 万円を乗じた金額の税額控除ができる措置を講じられます。
(注)上記ロの措置は、事業主都合による離職者がある場合及び風俗営業等を行っている場合には、適用されません。
ただし、上記イ及びロによる控除税額は、当期の法人税額の30%から現行の雇用促進税制による控除税額と上記①の税額控除制度による控除税額との合計額を控除した残額を上限とします。
地方税の計算では、中小企業者等に該当する場合は、税額控除後の法人税額を基礎に法人住民税を計算することになります。
国家戦略特区
国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除制度について、国家戦略特別区域法令の改正を前提に、次の見直しが行われます。
- 特定中核事業に革新的な情報サービスを活用した農業の生産性向上に係る研究開発に関する事業が加えられます。
- 特定中核事業以外の事業にインターナショナルスクールの整備に関する事業を加えた上、対象資産にその事業の用に供される貸付用の建物等が加えられます。
また、法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用除外措置について、国家戦略特別区域法の改正を前提に、対象に、国家戦略特別区域内における認定区域計画に定められた同法の特定事業に係る一定の要件を満たす再開発事業を行う民間事業者に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該再開発事業の用に供されるものが加えられます。
法人事業税の税率の改正
資本金の額又は出資金の額1億円超の普通法人の法人事業税の標準税率が、次のとおり変更されます。
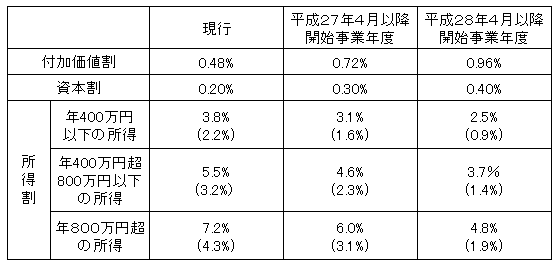
なお、所得割の税率下段のカッコ内の税率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率で、実際には下段の数字を利用します。また、現行と記載されている税率は、平成26年10月1日以後開始する事業年度に適用される税率です。さらに、東京都では、標準税率ではなく、超過税率を利用しています。実際に地方税の申告をする際に利用する税率と大綱で公表している税率とは一致しないので、全体のイメージを掴むくらいの感覚で見ていただく必要があります。
所得割の税率が低くなり、付加価値割と資本割の税率が高くなる方向であり、所得に対する負担を軽くしようという方向性がみてとれます。
地方法人特別税の税率の改正
資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率が、次のとおり変更されます。
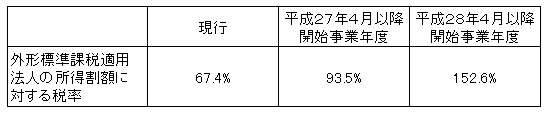
資本割の課税標準の見直し等
現行の外形標準課税の資本割は、「資本金等の額」に税率を乗じて計算されます。平成27年4月以降開始事業年度については、「資本金等の額」が「資本金に資本準備金を加えた額」を下回る場合は、「資本金に資本準備金を加えた額」を課税標準とすることになりました。自己株式の買取りなどで、「資本金等の額」が小さくなっている法人にとっては、大きな影響がある改正です。
また、法人住民税の均等割についても、現行は「資本金等の額」によって判定していますが、この点についても改正があります。「資本金等の額」に無償増減資等の金額を加減算する措置が講じられ、その「資本金等の額」が「資本金に資本準備金を加えた額」を下回る場合は、「資本金に資本準備金を加えた額」が均等割の税率区分の基準となります。こちらも、実務的には影響が大きいと思われます。
付加価値割における所得拡大税制の導入
平成27 年4月1日から平成30 年3月31 日までの間に開始する事業年度に国内雇用者に対して給与等を支給する法人について、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が3%以上(平成28 年4月1日から平成29 年3月31 日までの間に開始する事業年度については4%以上、平成29 年4月1日から平成30 年3月31 日までの間に開始する事業年度については5%以上)で、下記のイ及びロの要件を満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できることになります。
イ 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額以上であること
ロ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を上回ること
この改正は、給与額を増大させることで法人税の計算で税額控除できる枠組みを作っているのに対して、外形標準課税では給与額を増大させることで、付加価値割が高くなることの矛盾を解消するものです。今年の税制改正大綱で、キーワードのように頻繁に登場する「賃上げ」を後押ししてくれることが期待されます。
その他
法人事業税の付加価値割及び資本割のウエイトが高くなることで、急激な負担増になることに備えて、付加価値割りが40億円未満の法人については、負担変動に対する軽減措置が設けられています。
国税である法人税について、繰越欠損金の控除限度額、繰越欠損金の期間、中小企業者等の試験研究を行った場合の税額控除制度、中小企業者等の所得拡大税制について、改正があったことを受け、地方税についても整合性を持たせるための措置が講じられます。
法人税率の引き下げ
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税率が現行の25.5%から、23.9%に引き下げられます
なお、中小法人、公益法人、協同組合等については、軽減税率の取扱いが2年間延長されることになりました。結果として、所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率は15%、800万円超の部分については19%の法人税率と、従来通りの取扱いとなります。
欠損金の繰越控除と制度等についての見直し
欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、次のように段階的に引き下げられることになりました。
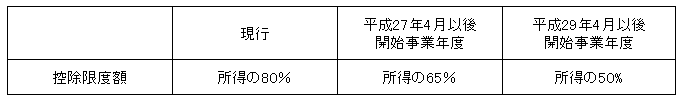
中小法人等については、従来通りで、控除限度額を所得金額までとする取扱いが存置されることになりました。
平成29年4月以後開始する事業年度から生ずる欠損金については、欠損金の繰越期間が現行の9年から10年に延長されることになりました。
受取配当金の益金不算入制度の見直し
益金不算入の対象となる株式等の区分及びその益金不算入割合については、次のとおりとなります。なお、大綱では、いつから開始かについて読み取れませんが、財務省の公表している資料によれば、平成27年4月以後開始事業年度から適用されるようです。
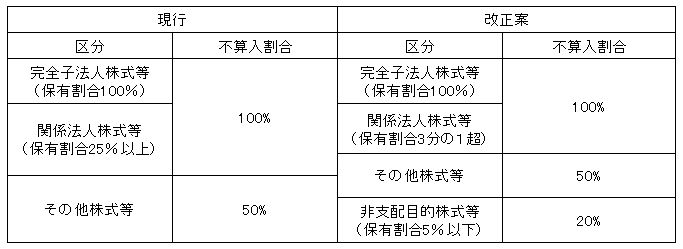
なお、公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額については、その全額を益金算入とします。ただし、特定株式投資信託の収益の分配の額については、その受益権を、上表の非支配目的株式等として、その収益の分配の額の20%相当額を益金不算入とします。
その他の株式等及び非支配目的株式等については、負債利子がある場合の控除計算の対象から除外されることになりました。
研究開発税制についての見直し
平成27年4月以後開始事業年度については、以下の措置による控除税額の総枠を当期の法人税の30%とします。
(1) 特別試験研究費の額にかかる税額控除制度
税額控除率を現行の12%から、(イ)特別試験研究機関等又は大学等との共同研究及びこれらに対する委託研究は30%、(ロ)それ以外のもの20%に引き上げます。
控除税額の上限を試験研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制とは別枠で5%とします。
特別試験研究費の範囲について、(イ)特別試験研究機関等のうち試験研究独立行政法人の範囲から国立研究開発法人を除外し、(ロ)特定中小企業者に対する委託研究の対象となる委託先の範囲に公益法人等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人等を加え、(ハ)特定中小企業者に対して支払う知的財産権の使用料が加えられます。
(2) 試験研究費の総額にかかる税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制
控除税額の上限を当期の法人税額の25%とします。
なお、繰越税額控除限度超過額及び繰越中小企業者税額控除限度超過額に係る税額控除制度は廃止されます。
所得拡大税制
平成25年度税制改正で導入された所得拡大税制は、平成26年度税制改正で要件が緩和され、平成27年度税制改正で、さらに要件が緩和されました。実務でも、適用できるケースがよくあります。また、大綱を見ていると賃上げという言葉が、キーワードのようによく出てきます。今回の改正では、中小企業者とそれ以外の法人に区分して、雇用者給与等支給増加割合に関する要件を緩和しています。改正後の増加割合は下記のとおりです。
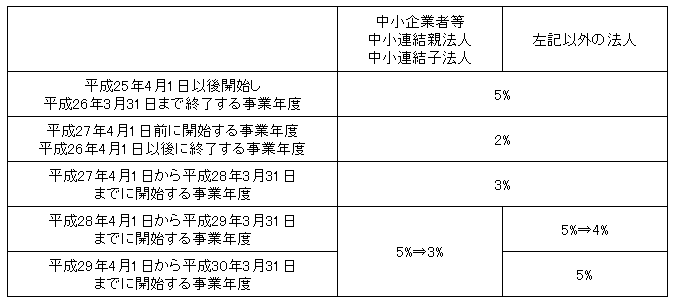
◆法人税の方向性が明確に!
法人税率の引き下げが折り込まれましたが、それ以上に、今後の方向性が明らかにされたところが興味深い内容となっています。
法人税率が25.5%から23.9%に引き下げとなります。実効税率という視点では、現行が34.62%ですが、平成27年度32.11%、平成28年度31.33%と方向付けており、利益が出ている会社を応援する姿勢が見て取れます。また、少し先をみると、実効税率を20%台まで引き下げ、一方で課税ベースを拡大するために、外形標準課税の強化、減価償却の定額法への一本化、法人事業税の損金不算入、租税特別措置法のゼロベースでの見直しなどが検討されています。
上記税率の引き下げ以外では、下記のようなものが気になるところです。
- 中小法人等以外では、平成27年4月開始事業年度から繰越欠損金の限度額が80%から65%へ、平成29年4月開始事業年度には50%に縮小されます。
- 平成29年4月開始事業年度から、繰越欠損金の利用期間が9年から10年に延長されます。
- 会社支配目的でない株式保有について受取配当金の益金不算入の割合が50%から20%に縮小されます。
- 外形標準課税において、付加価値割と資本割りのウエイトが高くなり、一方で所得割のウエイトが低くなります。
所得税関係
注目されていた、配偶者控除関連の変更は見当たりませんでした。制度の拡充としては、未成年者向けのNISA制度が設けられます。全く新しい制度として、海外へ移住する場合に、保有する有価証券等の含み益に課税する仕組みが創設されました。
ふるさと納税は、地方創生の推進につながるので、控除額の上限を引き上げ、確定申告不要な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられます。
国外に多数の扶養家族がいる場合にその確認が難しいことが問題視されていました。そこで、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等が義務化されます。
相続税・贈与税関係
平成27年から相続税の基礎控除が下がるため、対策をされている方も多くいらっしゃいますが、今年の改正を見ると贈与が随分しやすくなったように思われます。
直系尊属からの住宅資金の場合、消費税10%段階であれば、良質な住宅用家屋を取得するための資金なら3000万円までが非課税となります。
20歳以上50歳未満の者へ、結婚・子育て資金の支払いに充てるために、直系尊属が1000万円までの金銭等を金融機関に信託した場合は、贈与税を課税しないという制度が設けられました。教育資金の贈与と似た制度ですが、贈与を行った者が死亡した場合は、相続税に組み込まれるため相続税対策としてのメリットは薄くなります。
消費税関係
平成29年4月から消費税率が10%に引き上げられます。それに伴い、転嫁対策措置法も平成30年9月30日まで延長されることになりました。
外国人旅行者向けの輸出物品販売場が免税手続カウンターを設置する事業者に手続を代行させる制度及び外航クルーズ船が寄港した際に臨時販売場を輸出物品販売場とみなす制度が設けられ、今まで以上に外国人旅行者向けの販売が行いやすくなります。
外国事業者がインターネットを通じて日本の消費者へ向けての電子書籍や音楽の配信などの役務提供ついて、日本の消費税が課税されることになります。
こんな場合に寄附金が認定される
税務の現場で寄附金が認定される場合は、一般的な寄附を行う行為とニュアンスが違うので注意が必要です。一般的には、寄附金を支払ったら寄附金となるというイメージですが、税務ではより広範囲に寄附金をとらえます。例えば、下記のような事例です。
|
具体例を書き出すときりがないのですが、寄附するというイメージよりも、適正な代金を設定しなかった場合に寄附金の認定が起こりえると考えてください。
実務上は、寄附するという認識のないまま、知り合いだから、取引先だから、子会社だから、少し便宜を図ったつもりが、寄附金の認定が行われることがあります。
寄附金の認定が起こるとどうなるのか?
仮に、寄附金として認定された場合は、本来、得られる適正な金額を益金に計上して、寄附金とみなされた部分のうち、損金算入限度額を超える部分は損金となりません。
例えば、受取利息を100万円計上すべきなのに、利息をとっていなかった場合には、下記のような、税務的な仕訳を行います。
![]()
受取利息は益金となり、寄附金部分は、損金算入限度額を超える部分は損金となりません。つまり、追加で法人税の負担が発生するということなります。経営者の立場からすると自分が善意で損をしているにも関わらず、追加で納税が発生するという、心情的には納得できない結果となります。
実務上は、寄附金を認定したとしても、損金算入限度額以内に納まるため、結果として、課税されないということもあり、表面化しない場合もありますが、注意を払っておきたい部分です。
なお、国外関連者に対する寄附金は、全額が損金不算入という取扱いがあります。国外に、子会社などを設立していた場合などは注意が必要です。親会社の従業員が、子会社の業務を行っていた場合などに、寄附金が認定され、全額損金不算入となれば、大きな税負担につながる可能性があります。
寄附金か否かの線引きは難しい
お金を貸して、利息をとっていないというような場合には、寄附金が発生していたことを認定するのは容易です。
一方で、新製品を開発してサンプルとして配布するとか、新規取引を始めるにあたり特別に割引を行うとか、不動産賃貸にあたりフリーレント期間を設けることは、ビジネスとして一般的に行われます。このような場合には、売上を得るために必要性があるものとして、通常寄附金の認定は行われません。
実務では、寄附金に該当するのかしないのかが、争点になります。値引きとして処理したところ、値引きが異常であるとして寄附金の認定がされたとの訴訟事例もあります。寄附金については、寄附金として認定される可能性について、気にする習慣をつけ、不安な場合は税理士に相談するなど、客観的な視点でチェックすることが不可欠です。
寄附金とは
寄付金という言葉自体は馴染みがあり、通常の日本語として定着しています。法人税法上は、「寄附金」という漢字を用いますが、法人税法では特別に定義規定をおいておらず、ほぼ一般的な寄付と同様の内容と理解してください。
会計処理をしていて、寄附金なのか交際費なのか判断に悩むケースがありますが、国税庁のサイトでは、交際費と寄附金の区分について、下記のように説明しています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5262.htm
交際費とは、得意先は仕入先その他事業に関係のあるものに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。 一般的に寄付金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄付金に含まれます。 したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄付金になるのかそれとも交際費になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判断する必要があります。
|
寄附金の相手先による分類
法人が支出した寄附金については、その寄附をする相手先によって、損金算入できる額が異なります。
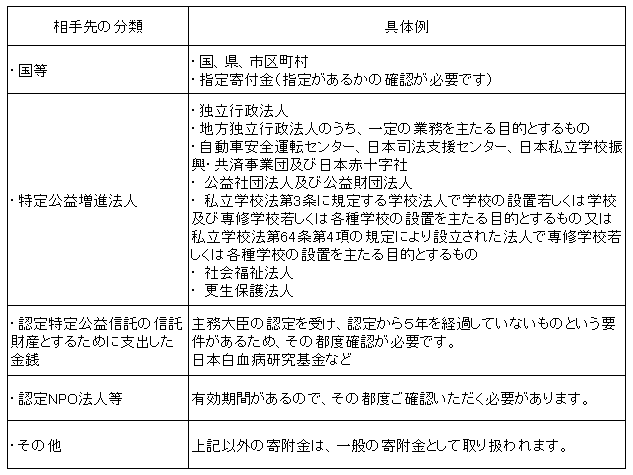
実務的には、国、地方公共団体、特定公益増進法人、認定NPO法人への寄附は、よくみかけます。注意点としては、NPO法人で「認定」が付かないところについては、一般の寄附金として扱われるので注意が必要です。また、学校法人へ寄附の場合で、代表者の母校への寄附金は、法人としての必要性が見いだせない場合などは、代表者への賞与と認定されるケースがあるため慎重に取り扱うべきです。
寄附金の損金算入限度額
寄附金を支出した場合の、損金算入限度額は下記のとおり計算されます。
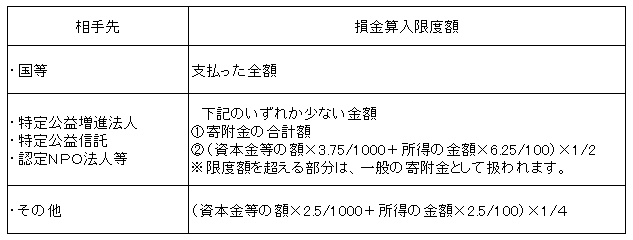
※ 事業年度が12ヶ月でない場合は、資本金等の額に1000分の3.75(又は2.5)の計算を行う際に調整計算が必要になります。
※ 所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
行為計算否認とは
行為計算否認という言葉を初めて聞くと意味不明ですが、税法では、重要なテーマの一つとされています。例えば、下記のような事例について、どのように感じられますか。
都内の一等地に親から相続した貸しビルがあり、多額の収入があり、所得税が最高税率で課税されている状態が前提です。 本来は、貸しビルの初留社の所得となるべき金額が、妻と子供に分散されることで、累進税率である所得税を随分と抑えられるかもしれない。 |
当事者間がどのような契約を結んでも契約自由の原則から、国家は干渉することができないと民法では学習します。契約自由の原則という考え方からすれば、賃料の60%を不動産管理料として支払うという契約自体は問題がないことになります。
一方で、税法の立場では、賃料の60%の不動産管理料は異常であり、妻と子供が役員をしている会社が相手だからこそ、異常な契約を結んだに過ぎないと判断します。この場合に、税負担が不当に減少しているとして、そのような「行為又は計算」を否認できるという取扱いがあります。
もっとも、まったくの他人間の取引にまで行為計算否認が適用される事は問題ですから、法人税法では、下記の三つの場面に限定して規定をおいています。
法人税法132条 同族会社等の行為又は計算の否認 |
行為計算否認については、上記のように限定した規定ぶりですが、まったくの無関係の者同士の取引なら、明らかに異常な取引であっても問題にならないのかというと、寄附金の認定や贈与の認定という別の形での対策がなされています。寄附金や贈与の認定については、別の機会にご紹介します。
行為計算否認の射程が変わる可能性
行為計算否認は、私法上の契約を否認して、課税を行うというものですから、慎重な運用がなされるべきとされています。納税者の立場からすると、身内との取引は常に否認される可能性があるということでは、同族会社は常に否認のリスクを気にしておくという非現実的な状況になってしまいます。
そこで、行為計算の否認が行われるのは、異常な取引について、「租税回避以外に正当な理由がない場合にのみ適用」されると、学説でも,裁判上も取り扱われてきたという長い歴史があります。
ところが、ヤフー事件の判決を受けて、その取扱いに変化が生じる可能性があります。今年の3月18日の地裁判決、11月5日の高裁判決では、租税回避以外の目的があったか否かではなく、結果として法人税負担の不当な減少があったという、結果に基づいた判決がなされているからです。
なお、ヤフー事件が、現時点では高裁判決がでた段階で、最高裁がどのような結果になるかは明かではありません。また、IBM事件では、今年の5月9日の地裁判決で、同じ行為計算否認に関して国側が敗訴しています。こちらについても、今後、高裁でどのような結果となるのかが注目されています。
この二つの判決次第では、行為計算否認について、税法の教科書の内容が大きく変わるかもしれないというくらい影響力がある内容です。
3つの通達についての改正案
従来から、書画骨とう等に対する取扱いとして、法人税基本通達7-1-1、連結納税基本通達6-1-1、所得税基本通達2-14に規定があり、減価償却資産に該当しないものについての取扱いを定めていました。
今回は、その取扱いを変更するものです。上記のように通達は3つありますが、内容がほぼ同じなので、法人税基本通達で改正前と改正案のものを比較すると、下記のとおりです。
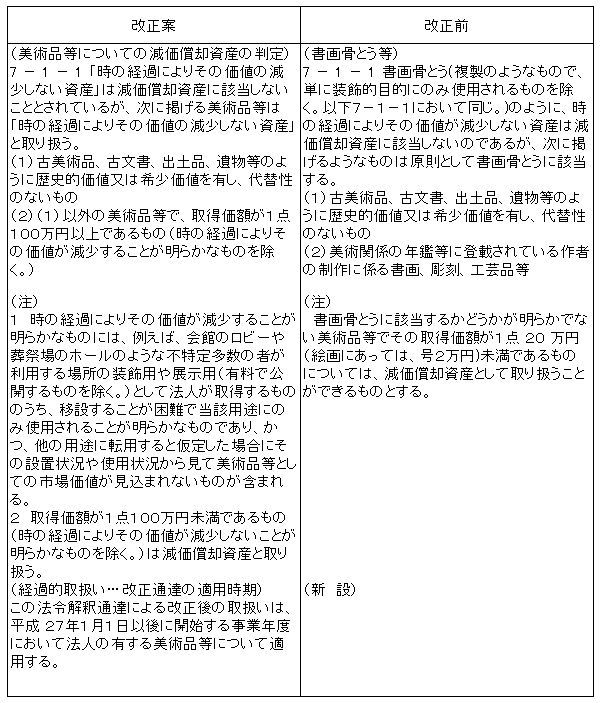
20万円から100万円に変更された金額基準
今回の改正で大きな点は、金額基準が従来は1点20万円未満(絵画にあっては、号2万円)という基準が、100万円以上という金額に改められたことです。実務上は、年鑑等に登載されていない限りは、書画骨とうに該当するか否か明らかでないとして、金額基準で判定せざるを得ないケースが多かったのではないでしょうか。20万円から100万円への金額基準の変更は非常に現実的な改正と思われます。
また、従来は、年鑑等に登載されている場合は無条件に減価償却資産に該当しないという判定でしたが、今回の改正では年鑑等に登載されているか否かは検討しなくてよくなっている点でも使い勝手がよくなっています。
平成27年1月1日以後に開始する事業年度から
この取扱いについては、平成27年1月1日以後に開始する事業年度において法人の有する美術品等について適用するとされています。つまり、これから取得するモノだけではなく、すでに所有しているモノについても、平成27年1月1日以後開始事業年度からは、税務上は償却可能となります。
会社によっては、まとまった減価償却費が計上できるケースも考えられます。仮に減価償却を行うとした場合は、室内に飾るものであれば、器具備品の室内装飾品として、主として金属製のものであれば耐用年数を15年、その他のものであれば耐用年数を8年とすればよいと思われます。
地方法人税法の創設
平成26年3月31日に交付され、平成26年10月1日から施行されている「地方法人税法」という新しい法律があります。名称は地方法人税法ですが、実際は国税であり、地方自治体ではなく、税務署に申告納付することになります。
名称が地方法人税で、国税というのは、矛盾があるように感じますが、次のような理由があります。法人の数が少ない地方では、従来の法人住民税だけでは税収として期待できないなど、大都市圏と比較すると、極端に税収が偏在する傾向がありました。そこで、従来まで、各地方自治体が課税していた法人住民税を小さくして、それに見合う金額を国税として国が徴収して、地方自治体へ再配分することを目的としているからです。
納税者にとっては地味な改正
地方自治体間では、大きく税収が減少する自治体、再配分により潤う自治体と、影響が大きな改正です。
一方で納税者側からすると、納税額総額は変更がないように設計されています。具体的には、下記のようなイメージとなります。
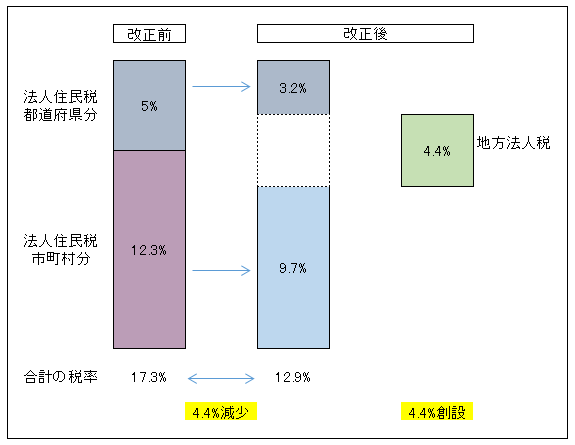
地方税としての法人住民税は、法人税の額に税率を乗じて計算しますが、都道府県民税分5%と市町村民税分12.3%だったものを、都道府県民税分3.2%と市町村民税分9.7%へ変更し、合計で4.4%税率を引下げます。一方で、国税である地方法人税として、法人税の額に4.4%を乗じた金額を納付することになります。つまり、トータルで考えれば、納税者が負担する税額には影響がないことになり、それほど注目度も高くなかったように感じます。
平成26年10月1日以降開始事業年度から適用
地方法人税については、平成26年10月1日開始事業年度から適用のため、通常の法人の場合は平成26年10月1日開始で、平成27年9月30日の決算から適用され、随分先のことのよう思われます。しかし、平成26年10月1日以降に設立した場合は、決算時期が12月、あるいは3月の場合でも、地方法人税の申告及び納税義務が生じます。
もっとも、申告書自体は、法人税の申告書の別表一(一)で、法人税の申告と同時に申告を行う形になりますので、正しい用紙を利用すれば、申告漏れとなることはないと考えられます。ただ、エクセルなどで独自に別表を作成している法人などは、新しい様式に合わせないと地方法人税の申告漏れに繋がりますし、法人税のソフトを利用している場合でも、10月以降設立の場合は、地方法人税に対応している別表かを確認しておきましょう。法人税のソフトで対応していても、用紙の選択ミスなどがあっては困るからです。
正しい別表か否かの確認方法は、別表一(一)の右側部分に、「平成二十六・十・一以後開始事業年度分」との記載があるかどうかでご判断いただければと思います。
新しい通勤手当の非課税限度額
交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当については、1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額という定めになっており従来通りです。もっとも、平成26年4月には消費税率の引上げがあった関係で、4月以降は通勤手当が上乗せになっているケースが多いかと思われます。
今回、手当てされたのは、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当です。自動車を利用する場合でも、4月以降ガソリンを購入する際に消費税率は引上げになっていますし、円安の影響でガソリン代も高くなっています。
改正後の非課税限度額については、下記のとおりとなります。
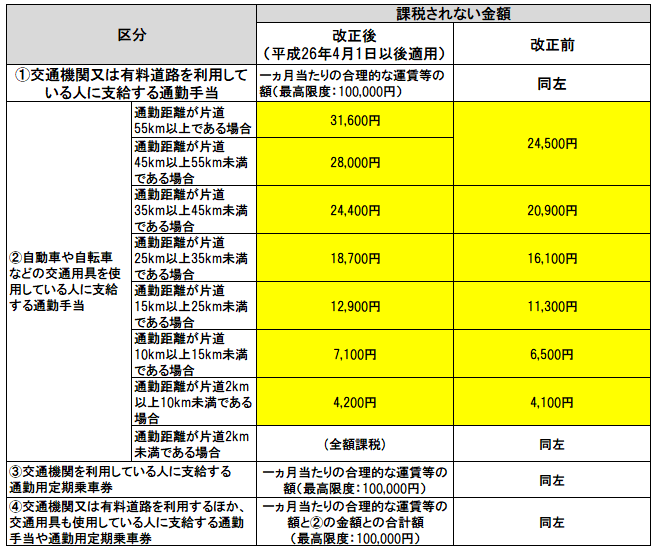
施行は平成26年10月20日なのに適用は平成26年4月から
今回の改正については平成26年10月20日施行ですが、上記の表にあるように平成26年4月1日以後適用とされています。このように、事後に定めた法令によって、遡って適用関係が変わる法律改正を遡及立法と呼びます。納税者に不利な改正の場合は、遡及立法は認められないものとされています。しかし、今回は、非課税枠が増加するという納税者に有利な改正なので遡及適用が行われています。
実務上の注意点
今回の改正は、4月に遡って非課税限度額が変更になりますから、4月以降の給与の支払いに関して源泉徴収した金額は、改正後の非課税限度額で計算した場合の源泉徴収すべき金額と異なる結果となる場合があります。この調整については、年末調整、若しくは確定申告で行うことになります。また、就業規則で、通勤手当は非課税限度額としている場合などには、差額の調整などが実務上必要となります。
- 非課税限度額を超えた通勤費を支払っていない会社は、今回の改正は無関係です。
- 一方で、非課税限度額を超えた通勤費を支払っている場合は、必ず調整が必要になります。
自動車通勤の場合に、高津比を一律で支払っているような場合には要注意です。
なお、中途退職などで、源泉徴収票を発行済みの場合で、改正前の非課税限度額以上の通勤費が支給されていた場合には、源泉徴収票の支給金額部分が変更になるので、再発行が必要となります。その場合には、摘要欄に再交付と表示することとされています。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
決算月に保険に加入した場合の取扱い
3月決算法人が、節税対策として、慌てて3月に保険に加入した場合に、本当に節税効果があるのでしょうか。理論的には、3月に加入して、3月から翌年の2月までの1年分の保険料を前払いしているという状況であれば、3月中に費用となるのは3月分だけで、4月から翌年2月までの保険料は、前払費用として資産に計上されることになり、利益の圧縮効果はありません。会計監査を受けている場合などは、厳密な処理を行うため、結果として費用を前倒しで計上するという効果は見込めないケースが多いです。
企業会計の考え方では、重要性の乏しいものであれば、前払費用として資産計上を行わず支出時の費用とする処理を認めています。この考え方を受けて、法人税基本通達でも下記のとおり定めています。
| 2-2-14(短期の前払費用) 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14おいて同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に参入しているときは、これを認める。(昭55直法2-8追加、昭61直法2-12改正) (注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の形状と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの運用はないものとする。 |
通達では、継続適用を前提に支払った日から1年以内に提供を受ける役務について、支払った日の損金とする処理を認めています。
一方で、支払った日から1年を超えて役務の提供を受ける場合や、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支払の場合は、この取扱いを受けることができません。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm
この取扱いを受ける場合の注意点は、前払いをして損金処理が認められるのは1年以内に役務提供を受ける部分だけということです。例えば、数年分の前払いをすると、逆に厳密な処理が要求されるので、節税対策としては使えなくなるという点です。
自賠責保険の取扱い
自動車保険の任意保険は、通常保険期間が1年ですから、支払時の費用として処理することが一般的です。
一方で、自賠責保険については、車両を購入した際や、車検の際に車検の期間に合わせて保険契約を結ぶことが日常的で、通常は1年を超える保険期間となります。自賠責保険の保険期間が2年、3年という場合、上述した法人税基本通達の取扱いから外れることになりますが、実務的には自賠責保険については、支払時の損金としてよいと言われています。
この根拠については、法令や通達からは直接読み取ることができません。しかし、法人税の事例集、国税OBの方が書かれた質疑応答事例などで、自賠責保険は法律上強制されているもので、金額的にも小さく、租税公課と同様な性格であることを理由として、支払時の損金とすることが、実務では一般的であるとして紹介されています。
終身保険
終身保険について、法人が契約を行い、被保険者を役員・使用人とした場合の、保険料の取扱いについては、下記のとおりです。
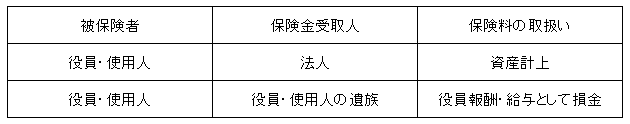
保険金について法人を受取人とする場合は、資産計上することになり損金扱いされません。一方で、保険金の受取人を、役員・使用人の遺族とする場合は、法人としては、役員報酬・給与として損金算入可能ですが、役員・使用人には給与所得として所得税等が課税されることになります。
なお、終身保険に特約を付けた場合は、特約部分は、損金算入されることになります。
個人的には、法人が税金対策で利用するタイプの保険ではないように思っています。ただし、一時払いの契約とすることで、解約返戻率を高くするなど、貯蓄の代替として利用しているケースなどは見受けられます。
ガン保険
ガン保険は、法人が契約者となり、被保険者を役員・使用人、保険金受取人を法人とした契約形態の場合、平成24年4月26日までの契約であれば、保険料の全額について、損金として取り扱われていました。契約してから短期間で、解約返戻率が高くなる商品が多くの保険会社から節税の定番商品として販売されていました。
しかし、平成24年4月27日以後の契約のものについては、保険期間の半分までは、2分の1だけしか損金算入できないとの取扱いとされ、従来ほどの節税効果が期待できなくなりました。
現在は、養老保険のハーフタックスプラン、定期保険などと比較して、状況に合わせて、節税に利用するといった利用形態となりました。
全額損金として取扱われなくなったことで、節税メリットは薄くなりましたが、契約から比較的短期間で、それなりの解約返戻率となるので、貯蓄性の高い節税商品として位置づけることが可能です。
保険会社によっては、従来のガン保険に替わる商品として、全額損金となる保険商品を販売しているケースがあります。しかし、解約返戻率が高くなるまでに時間を要するなど、従来のガン保険ほど節税商品としては使い勝手が良くありません。この当たりは、課税庁とのイタチごっこで、節税効果が高い商品が販売されれば、規制されるということで、なかなか難しい事情があるようです。
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済は、独立行政法人中小企業基盤機構が扱っている共済制度です。本来の趣旨は、取引先の倒産などで、回収困難となった売掛金が生じた場合に、掛金総額の10倍までの資金を借りることができるというもので、連鎖倒産を防止することです。共済金の借入は、無担保・無保証人である点が特長です。
経営セーフティ共済の掛金は、全額損金扱いとすることが認められています。また、解約する場合でも、掛金納付月数が12ヶ月以上ある場合は解約手当金が支払われることになり、掛金納付月数が40ヶ月以上の場合、掛金の100%が解約手当金として支払われます。
全額損金算入で、40ヶ月掛金を支払えば100%の解約手当金というのは、独立行政法人が行う公的な施策であり、特別な取扱いと位置づけるべきです。生命保険ではありませんが、経営セーフティ共済が利用可能なら、節税対策としては、もっともお勧めの商品です。もちろん、本来の趣旨である連鎖倒産から会社を護るという意味でも大きな効果が期待できます
養老保険の税務上の基本的な取扱い
法人が契約者となる養老保険については、死亡保険金及び満期保険金の受取人を誰とするかで、取扱いが異なってきます。基本的な契約形態は、下記のとおりです。
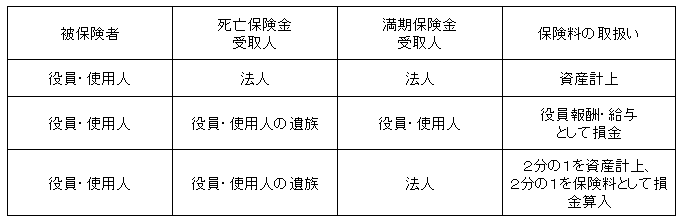
上記の中でも、死亡保険金の受取人を役員・使用人の遺族、満期保険金の受取人を法人として契約する場合は、支払保険料の2分の1が損金として認められる一方、満期になれば概ね支払った金額以上の満期保険金を受け取ることが可能なため、節税メリットを受けつつ貯蓄ができるので、非常に利用されるケースが多いです。2分の1が損金にできることから、ハーフタックスプランと呼ばれることもあります。
なお、ハーフタックスプランを利用する為には、「役員・使用人の全員」が加入することが要件となっており、特定の役員・使用人だけを保険の対象とした場合は、2分の1は役員・使用人に対する役員報酬又は給与として取り扱われるので注意が必要です。
ハーフタックスプランは、節税と貯蓄が両立できて魅力的ですが、従業員が定着しない場合などは、従業員の退職に伴い短期間で解約することになるため、保険料に比べて解約返戻金が極端に低くなる場合なども考えられます。デメリットについても十分な検討が必要です。
逆ハーフタックスプラン
上記の表をみて、契約の形態として、死亡保険金を会社が受取人として、満期保険金を役員・使用人とする形がない点についてお気づきでしょうか。実は、国税庁などの資料では、下記のとおり、三つの類型しか紹介されていません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5360.htm
養老保険で、死亡保険金について被保険者の遺族が受取人となり、満期保険金は会社が受け取るというのは、福利厚生として自然な形です。一方で、死亡保険金は会社が受取人となり、満期保険金を被保険者が受取人となることは、自然な形ではないので、想定されていないのかもしれません。一般的には、下記のように取り扱われるとされています。
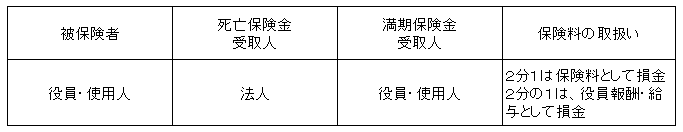
法人からすれば、2分の1が保険料、2分の1が役員報酬又は給与として、全額が損金となり、節税効果が期待できます。個人の立場からは、2分の1は給与として課税されることになりますが、裏を返せば2分の1部分は課税されないことになります。もっとも、保険が満期になった際は、一時所得として、下記の計算式により所得を計算し、所得税が課税されることになります。
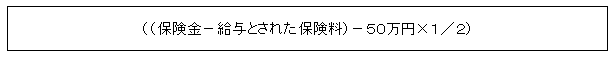
一時所得の計算は50万円控除して、さらに2分の1にするので、実質2分の1未満しか課税されないことになります。所得が大きく税率が高い人にとっては、給与として直接受け取るよりも、保険を経由することで、税負担を抑えるというメリットが生じます。
上手に活用できれば魅力的な部分もありますが、被保険者の立場からは受け取る現金がないにも関わらず、所得税と住民税の負担が生じますので、税金の先払い状態が生じます。さらに、資金繰りの都合で保険を解約した場合は、会社が解約返戻金を受け取ることになりますが、被保険者からすれば課税された所得税と住民税が戻ってくる訳ではありません。
法人にとって全額が損金となり、被保険者にとっても所得税の節税に繋がるということで、良いことずくめに見えますが、途中解約などの場合にはデメリットも大きいことを理解しておく必要があります。
個人的には、ハーフタックスプランは、元気な会社に気軽に進められるプランですが、逆ハーフタックスプランについては、慎重な判断が求められると考えています。
定期保険の基本的な取扱い
生命保険のうち定期保険と呼ばれる保険を法人が契約した場合の、保険料の取扱いについては、基本的には下記のように取り扱われます。
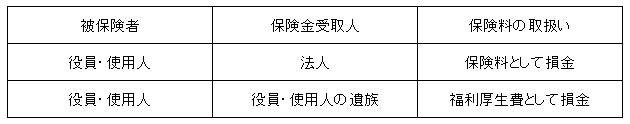
定期保険は、満期保険金がなく基本的には掛け捨てタイプなので、法人税法上は損金処理される点が特長です。
役員・使用人を被保険者として、法人が保険金受取人となる場合は、役員・従業員が死亡した場合に、退職金の原資とすることを想定して契約することが多くあります。
一方で、福利厚生の一環として、被保険者の遺族を保険金受取人とする契約形態でも、福利厚生費として損金算入が認められます。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを対象とする場合は、本来は個人で契約すべき保険料を肩代わりしているに過ぎないとして、その役員・使用人に対する給与となります。結果としてその役員・使用人には、所得税が課税されることになるため注意が必要です。
定期保険でも一部損金算入が制限される契約形態
定期保険は、一定期間に死亡事故が発生した場合、死亡保険金が支払われるもので、満期保険金はありません。しかし、定期保険の場合でも、途中で解約した場合に解約返戻金が支払われるケースがあります。保険期間が短い場合は、解約返戻率も低く、全額損金算入としても弊害はないのですが、保険期間を長くすることで、一定期間の解約返戻率を高く設定する保険商品が販売されています。このような保険については、国税庁がホームページで取扱いを公表しており、内容としては下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm
(1)長期平準定期保険(長期間、保険金額が一定の定期保険)
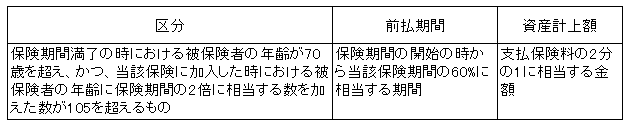
(2)逓増定期保険(保険金が保険期間の経過と共に高くなる定期保険)
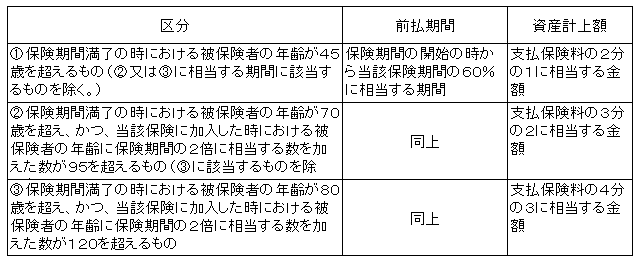
なお、この取扱いについては、平成20年2月28日以後の契約に関するもので、それ以前の契約に関しては異なる取扱いとなります。
実務では、保険会社が用意してくれる資料等に詳しく解説がされています。
特約保険料について
定期保険に、疾病特約や入院特約などを付すケースがあります。特約を付した場合でも、基本保険料に準じて損金として取り扱われます。特定の役員・使用人の遺族を死亡保険金の受取人としている場合に、給与として所得税の対象となる点も同様です。
特約について、気をつける点があります。役員を被保険者とする場合に、疾病特約や入院特約が付されていて、会社に特約に対応する保険金が入金された場合、法人の益金となりますが、それを役員に支払う場合に、定期同額給与に該当せず損金算入が認められないということが想定されます。特約の保険金を受け取った場合の課税関係まで、十分に検討を行う必要があります。
生命保険と損害保険
保険と言われると、社会保険、民間の保険など、いろいろな分野があります。民間の保険については、大きく生命保険と呼ばれる分野と、損害保険と呼ばれる分野があります。簡単に説明すると、人に関わるものは生命保険の守備範囲、モノに関わるものは損害保険の守備範囲ということになります。さらに、病気や怪我に対する保険商品などもあり、微妙に線引きは曖昧となっています。
今回は、生命保険の基本的な3つのタイプの保険について、ご紹介します。多くの保険商品は、3つのタイプのどれかに当てはまるか、あるいは組み合わせた形となっています。
生命保険の3つのタイプ
(1)定期保険
定期保険は、一定期間に死亡した場合に、保険金が支払われるタイプの生命保険です。保険期間を一定期間とすることで、保険料を低く抑えることができるのが特長です。
一般的に掛け捨てタイプの保険であり、満期保険金はありません。ただし、途中で解約した場合に解約返戻金を受け取れる場合があります。
法人での利用形態としては、従業員に何かあった場合に、遺族へ退職金を支払うための原資として定期保険を利用するケースがよくあります。保険料が割安で、まさに補償を買うというイメージです。
(2)終身保険
終身保険は、一生を通じて、死亡保険金が支払われる保険です。一生を通じて、死亡保険金が支払われるということで、貯蓄に近い性格を有します。
例えば、貯蓄では、働き盛りの頃に死亡した場合など、遺族にとって多額のお金が必要な時期に、貯蓄が十分でないという根本的な問題が生じます。そのような、貯蓄のデメリットを埋めるような性格を有しています。
ただし、契約を続けていれば、保険金が必ず支払われる保険ですから、定期保険に比べると、保険料が割高になります。
法人での利用は、あまり一般的ではありません。なぜなら、契約形態によって、資産計上か、被保険者の給料として扱われるため、税メリットが享受できないからです。さらに、貯蓄の代替として考えた場合も、早期に解約した場合は、支払保険料に対して解約返戻金が低くなるというリスクもあります。また、補償の購入という意味では、死亡より前に定年を迎えることが一般的ですので、法人にとっての補償としては適さないという事情があります。
終身保険は、若いうちに、個人で加入するのがよい保険だと筆者は考えます。
(3)養老保険
養老保険は、保険期間中に被保険者が死亡した場合には死亡保険金が支払われ、一方で被保険者が生存したまま満期を迎えれば、満期保険金が受け取れるという仕組みの保険です。貯蓄と補償、両方のメリットが享受できます。
貯蓄性が高いという意味では、終身保険と似ていますが、満期までの期間を5年、10年、20年などと、任意に設定できるので、法人としては契約しやすい保険です。さらに、契約形態によっては、支払保険料の2分の1を損金経理できるので、節税の手法としても利用されます。
実際に保険が販売される場合には
基本形は、定期保険、終身保険、養老保険の3つですが、実際に保険が販売される場合には、定期保険と終身保険を組み合わせて、定期付終身という形で販売されることがよくあります。
定期付終身という形での保険の販売は、当初20年の間は子供の学費など、補償を厚くする必要がある場合に、200万円の終身保険に、保険金5000万円の定期保険を特約として付けて販売するという形態です。補償が必要な時に補償が厚く、その後は保険金額が小さくなるけれども一生涯にわたって保険金が支払われるという契約者のニーズに合わせた商品です。
また、終身保険や定期保険に、病気になった場合などの特約を付けて販売されることも多くあります。例えば、三大疾病特約やガン特約などを付けて販売するケースです。
さらに、定期保険といっても、保険金額を一定額とするものもあれば、保険金額が期間の経過と共に増加していくタイプ、逆に期間の経過と共に減少していくタイプ、保険期間が短いもの、長いものと、いろいろな商品が販売されています。これに対応するために、法人が保険料を支払った場合の取扱いは、実に細かい内容になっています。
次回以降、法人が保険料を支払った場合の取扱いについて、ご紹介していきます。
保険料が節税になる理由
よく保険会社の営業の人から、節税の手法として保険契約を奨められます。なぜ、保険契約が節税の手段としてよく用いられるのかというと、支払った保険料のうち費用として処理される額が、利益を圧縮し、結果として法人税を節約する効果があるということです。
税率が30%であれば、全額費用扱いできる1000の保険料を支払っても、節税効果は300ですから、持ち出しが増えてしまいます。しかし、保険の種類によっては、それなりの解約返戻金が期待できるので、解約返戻金を考慮すると、貯金をしつつ、法人税も安くできるというような、節税の仕組みができあがります。
保険節税の落とし穴
保険は節税に利用できることは、事実です。しかし、思い通りにならないというケースもしばしば登場します。
保険節税は、保険料の支払時に節税効果がありますが、解約返戻金を受け取れば法人税が課税されるので、出口対策が重要になります。多くの場合は、役員退職金の支払いが想定される時期に、解約返戻金のピークを合わせて、受け取る解約返戻金は収益になるけれども、役員退職金としてそれ以上の額を支払うことで、法人税の負担が実質ないような形をとります。退職金については、所得税が優遇されるので、トータルではかなりの節税が期待できます。
予定通り事が運べばうまく節税として機能するのですが、保険の契約時期から退職金の支払時期まで相当長期間である場合には、業績の悪化などで、保険料を払い続けることができずに解約せざるを得ないということも考えられます。短期間で解約すると、ほとんど解約返戻金が受け取れない場合などもあり、計画通りに進まない場合には、節税どころか、損をしてしまうこともあります。多くの会社を見てきましたが、10年間ずっと業績が良い会社というのは、極めて少数です。10年以上、保険料を払い続けるのが保険料節税ですから、予定通りに事が進まないということも想定して実行する必要があります。
保険の種類によって取扱いが異なる点に注意
保険料を払えば、費用になるかというと、保険の種類によって、異なる取扱いとなります。一般的には、解約返戻金がない、掛け捨てタイプの保険であれば費用として取り扱われます。一方で、貯蓄性の高い保険、具体的には終身保険や養老保険などについては、保険料を支払っても資産計上を行うというのが基本的な取扱いとなります。
養老保険については、役員や従業員を被保険者とし、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人を法人とすることで2分の1を損金にできるとか、本来は費用処理できるはずの定期保険が、契約形態によっては、一部を資産計上しなければいけないなど、保険料に関する税務の取扱いは複雑です。
保険に対する税務を説明する前に、保険の種類を説明する必要がありますので、次回は、保険の種類についてご紹介していきます。
マイナンバーの概要
マイナンバーは、住民票を有する全ての人を対象に1人に1つの番号が割りあてられます。番号は12桁で、平成27年10月に住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られてくる予定です。原則として、マイナンバーは、変更されず一生利用する個人の識別番号となります。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、法律で定められた行政手続にしか使えないこととされています。
税金に関連して、納税者番号制度の導入について、以前から検討されてきました。マイナンバーは、税金だけでなく社会保障などより広い場面で利用される点が納税者番号とは異なりますが、税の世界に限定して見れば納税者番号と同様の役割を持つことになります。
マイナンバーの利用
内閣府が公表している、マイナンバーが必要になる行政手続は下記の通りです。
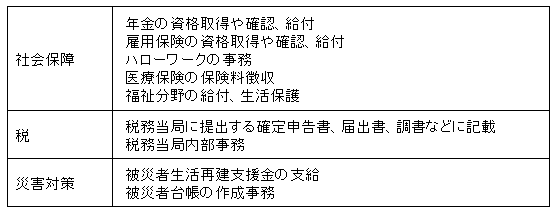
上記をみると、行政側が利用するだけのように見えるかもしれませんが、民間事業者がマイナンバーを源泉徴収票や支払調書の作成時に記載するなどの場面が生じます。事実上、会社で従業員のマイナンバーを把握しておき、所定の手続の際に従業員のマイナンバーを記載するという実務となります。また、支払調書へマイナンバーを記入するということは、個人外注に対する支払がある場合や、保険会社が保険金の支払いなどをする際にも、マイナンバーを確認するなど、支払いを行う際には、マイナンバーの確認作業が必要となります。
さて、マイナンバーの確認はどのように行うのかという疑問が生じます。マイナンバーの通知後に市町村に申請することで、個人番号カードが交付されることになりますので、個人番号カードを確認しての作業となります。正しく確認作業を行わないと、他の人の番号で支払調書を作成してしまい、後日、税務署から氏名と番号が不一致であるとの問い合わせが来るなどの状況が想定されます。マイナンバーを正しく確認して管理しておく仕組み作りが必要となりそうです。
法人番号
マイナンバーは、個人に通知される番号ですが、法人番号の利用も同時にスタートします。こちらは、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁加えた13桁の番号となります。具体的には、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る法人税申告から法人番号を記載するようになります。
法人番号は、個人番号と異なり利用制限がないので一気に普及する可能性があります。実際に法人番号は、インターネットを通じて公表されることが予定されています。
法人番号については、平成27年10月以降、国税庁長官から通知される予定となっています。
税に対する影響
源泉徴収票を作成する際に、マイナンバーの記載が必須になれば、複数の会社から給料を受け取っている場合、転職などがあった場合の前職分の給与など、課税漏れが限りなく起こりにくくなります。また、支払調書など、電子申告を利用していない場合には手作業で行われていると推定される名寄せ作業が、マイナンバーで統一管理されるので、集計漏れや他人名義で名寄せされてしまうなどの間違いがなくなります。
また、個人番号と法人番号を活用すれば、消費税についてインボイス方式に近い方式へ移行することも容易です。消費税の複数税率なども現実味を帯びます。さらには、課税漏れが起きやすいとされているネットビジネスや、最近話題となった外れ馬券に対応して、新たな税制を構築することも容易です。
一方で、個人番号で検索すれば、課税庁が、給与、保険金、株式の売却、年金など個人番号と紐付けできるものは、全て把握できてしまうという怖さも感じるところです。
全体的な方向性
1つ目は、日本企業の国際競争力を高めるために、課税ベースを拡大しつつ、税率を引き下げるという内容です。2つ目は、法人税の負担構造を改革する事により、広く薄く負担を求める構造へ変化させることであり、租税特別措置法についてゼロベースで検証していくこととする内容です。それ以外では、地方法人課税についても、広く薄く負担するという趣旨から、外形標準課税をより広く適用するような見直しが必要であるとしています。
現状は、多くの法人が赤字であり法人税の納税を行わず、地方税の均等割額のみを納税している状況です。つまり、黒字法人のみに税負担が偏っているという問題があります。そこで、黒字法人の税負担を軽くする必要があるので税率を下げることにし、一方で、その財源として、現在納税を行っていない法人から課税できる仕組みを構築するというものです。
具体的な検討事項の要約
法人税改革についての内容を要約すると下記の通りです。私のお客さんは、中小法人が多いので、少し厳しく感じました。
期限のある措置法は、原則期限到来時に廃止、期限がない措置法は期限を設定して対象をより小さくする見直しを行う、利用実態が特定の企業に集中している政策税制や、適用者数が極端に少ない政策税制は、廃止を含めて根本的な見直しを行う。
【2】欠損金の繰越控除制度の見直し
繰越欠損金の繰越控除期間を延長し、控除上限額を引き下げる見直しを行うこととする。なお、それに伴って帳簿の保存期間の延長が必要となる。
【3】受取配当金等の益金不算入制度の見直し
支配関係を目的とする株式の保有に伴う配当収益を課税対象から外すべきである。
【4】減価償却制度の見直し
定率法を廃止し、定額法に一本化すべきである。
【5】地方税の損金算入の見直し
財源確保の一環として、地方税の各税目の性格や事業者への影響を勘案しつつ、地方税の損金算入の見直しについて、具体的な方策を検討すべきである。
【6】中小法人課税の見直し
①中小法人の範囲について
現在資本金1億円未満となっている水準を引き下げ、段階的な基準の設置を検討する必要がある。
②軽減税率について
所得金額800万円以下の金額に適用される軽減税率は厳しく見直すべきである。また、措置法で設けられている軽減税率についても、リーマンショック後への対応として設けられたものであり、その役割は終えている。
③その他特例措置について
租税特別措置法と同様に見直しを行う必要がある。
④いわゆる「法人成り」について
・給与所得控除について、さらなる検討が必要である。
・軽減税率を見直すことで所得税とのバランスをとる必要がある。
・中小法人について適用除外されている留保金課税について検討が必要である。
【7】公益法人課税等の見直し
公益法人以外の法人とのバランスから、公益法人等の範囲や収益事業の範囲を見直すべきである。また、軽減税率とみなし寄付金制度の適用は過大な対応であり、見直しが必要である。さらに、配当や金融資産収益については、会費や寄付金収入とは異なり、発生した収益として課税のあり方について検討すべきである。
【8】地方法人課税の見直し(法人事業税を中心に)
現在は資本金1億円超の法人を対象に外形標準課税が採用されているが、対象法人の拡大を行うべきである。また、外形標準課税の計算については、所得に対する税負担を軽減し、付加価値割の比重を高めるべきとしている。資本割についても、付加価値割に振り替えることが望ましいとしている。
現在、資本金の額と従業員数に基づいた区分に応じて課税されている法人住民税均等割りについて増額し、法人所得に対する税負担を軽減することが望ましいとしている。
飲食費の範囲
まず、最初に注意したいのが飲食費のうち社内飲食費は除かれている点です(Q2)。飲食費に該当する場合でも社外の人が参加していないと、損金算入は認められないことになります。なお、出向者については、どのような立場で出席するかによって、社内飲食費に該当する場合と、該当しない場合があるので注意が必要です(Q5)。
また、実際に飲食費であっても、ゴルフや観劇、旅行等の催事の一環としての飲食等については、飲食費に該当しないこととされています(Q3)。
帳簿書類への記載事項
飲食費を損金算入するためには、事実として飲食費であることはもちろんですが、帳簿書類に飲食費であることを明らかにするためにつぎの事項が記載されている必要があります(Q6)。
イ 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
ロ 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
なお、上記ロについては、参加者が多数の場合は、〇〇部長他10名といった記載でも差し支えないとされています。また、氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略しても差し支えないとされています(Q7)。
1人当たり5,000円以下の飲食費の取扱い
交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外するという取扱いがあります。こちらに該当すれば、50%相当額ではなく、全額が損金算入可能となります。この取扱いについては、下記をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
中小法人の取扱い
中小法人に該当する場合は、年間に800万円までの交際費等については、全額の損金算入が認められる定額控除限度額を用いる方が多くの場合は有利になります。ただし、中小法人に該当する場合でも、接待飲食費の額が年間で1,600万円を超えるような場合には、接待飲食費の額の50%相当額を損金算入する制度を利用する方が有利となります。中小法人でも、交際費が多額に及ぶような場合は、接待飲食費を区分しておくなど、有利な制度を適用できる準備をしておくことが必要となります。
区分経理について
日本の消費税は、請求書等の保存義務を課し、帳簿による消費税の計算を行う仕組みとされています。つまり、帳簿方式による消費税の計算システムを採用しています。
一方で、複数税率を実施しているEU諸国ではインボイス方式という、インボイスを元にした消費税の計算システムを採用しています。簡単に説明すれば、インボイスを集計すれば消費税の計算ができるという消費税の計算システムです。
複数税率を採用した場合、帳簿による計算を行うと区分経理が必要となり負荷が増大することになります。計算だけであれば財務会計システムを使用すれば可能ですが、その計算が正しいことを担保するために請求書等の保存が必要になります。この場合に、請求書が間違っていた場合の責任の所在など、請求書を発行する側にどの程度責任を持たせるかという問題が生じます。
経理の事務負担を軽くする趣旨からは、インボイス方式が望ましいという話しになります。インボイスを集計すれば消費税が計算できるのであれば、区分経理などの経理的な負担は軽くなります。ただし、諸外国では、インボイスを発行する側に重い責任を負わせ、また免税事業者にはインボイスを発行させないという対応がとられています。
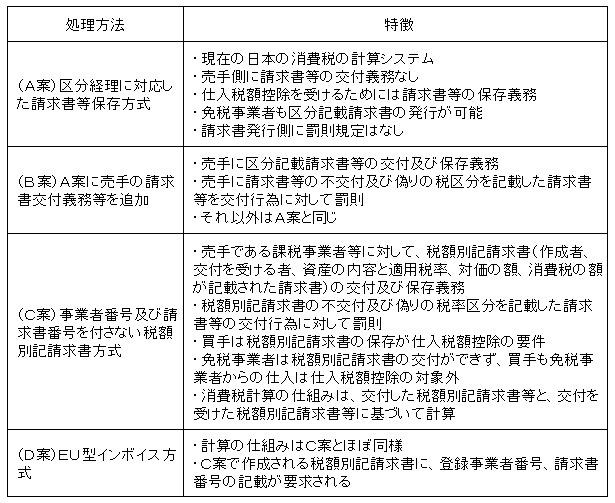
A案とB案の違いは、請求書発行側に罰則規定があるか否かで、基本的には現在の消費税の計算の仕組みと同じです。C案とD案は、インボイス方式と一括りに考えて良いと思います。異なるのは、税額別記請求書に登録事業者番号と請求書番号の記載があるか否かで、税務行政側の立場からは、事業者番号と請求書番号の記載があることで、不正の防止、不正発覚に大きく寄与するという特徴があります。
◆簡易課税とマージン課税について
(1)簡易課税の適用について
事業者は、新たに細分化された業種毎に売上を区分して、それぞれにみなし仕入率を適用することになります。
諸外国の例を見ると、フランスは簡易課税制度を採用していません。ドイツとイギリスでは簡易課税と似た仕組みが導入されています。そして、ドイツでは業種区分が40区分、イギリスでは業種区分が17区分であることが資料では紹介されています。
業種区分が細分化されることは、簡易課税の本来の趣旨である中小事業者の事務負担の軽減という趣旨に反することになります。
(2)マージン課税制度
聞き慣れない言葉ですが、日本では現在採用されていない制度です。インボイス方式を採用して、免税事業者がインボイスを発行することができない仕組みとなった場合に、消費者や免税事業者からの仕入については、仕入税額控除が認められないということになります。具体的には、中古自動車販売業者、質屋、古物美術商、古本屋などの中古品取引を行う事業に大きなインパクトを与えてしまいます。
そこで、欧州諸国では、特定の業種へのインパクトを与えてしまうことを避ける観点から、中古品の販売については.マージン(売価-仕入価格)のみを課税対象とする特例が設けられているそうです。古物等の譲渡に係る課税標準額は、試案では下記のように示されています。
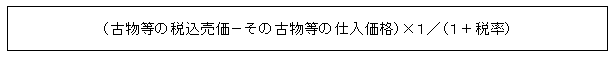
また、実務的には、少額な中古物品を消費者から購入した場合の記帳義務を課す必要が生じます。
一般的な軽減税率へのイメージと報告書のスタンス
お客様と、会話していると「軽減税率」に対して好意的な意見を持たれている方が、多くいらっしゃいます。なんとなく、消費者に優しいイメージに映るのでしょう。
消費税は、広く薄く一律に課税する仕組みとなっていますから、どうしても経済的弱者が不利になる性格を有し、逆進性が強い税であると理解されています。軽減税率が有効に機能すれば、消費税の問題とされる逆進性を緩和できる可能性があります。
報告書では、「どの案が有力ということではなく、国民の議論の材料とするため、考え得るパターンを機械的に示すものである。」としており、現時点では白紙の状態と考えて良いと思います。報告書の中では、論点を大きく三つに別け、①何を軽減税率の対象にして、軽減税率により減少する税負担をどのように確保するかという問題、②軽減税率を導入するにあたってどのような経理処理を適用すべきかという問題、③簡易課税適用者に対するケアと中古品販売業者についてのケアの問題を紹介しています
何を軽減税率の対象とするのか
報告書の中では、仮に飲食料品を軽減税率の対象とする場合に、どこまでを含めるのかという点について、下記のように8パターンを例示しています。
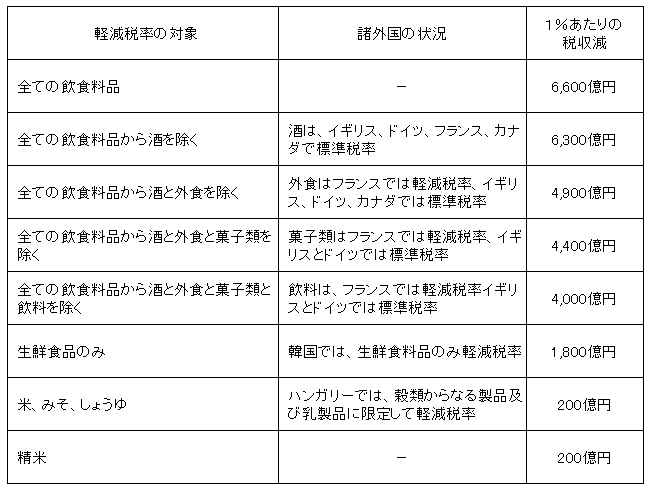
報告書では、飲食料品について軽減税率とする場合について、検討を加えていますが、飲食料品だけでも、上記のように様々なバリエーションが考えられます。例えば、外食を標準税率とする場合に、報告書の中で問題点として指摘しているのは、「牛丼屋の牛丼は標準税率、すき焼き用のブランド牛は軽減税率」という線引きになる点について、バランスとして良いのかという疑問です。
さらに、実際に軽減税率を導入という場合には、飲食料品だけではなく、生活必需品に対する軽減税率も比較検討する必要があり、その線引きの難しさを考えると、導入の難しさが際立ちます。
また、消費者の目線からすれば、できるだけ多くの品目について軽減税率が導入されると、負担が和らぐような気がします。しかし、上記の表に記載したように、軽減税率の品目を増やせば、大きな税収減となり代替の財源を必要とします。諸外国では、軽減税率を採用していると同時に、標準税率が日本の消費税率よりも高いという点も気にしておく必要があります。
軽減税率が、うまく機能すれば逆進性の緩和という効果は、期待できますが、一方的に負担が軽くなるのではなく、別の部分での負担は重くなる側面もあるのだと言う点が、軽減税率の議論をする際に重要となります。
棚卸は利益確定のための最も重要な手続
利益の計算を行う際に、売上に対応する原価、つまり売上原価を計算する必要があります。そして、売上原価を計算する場合は、一般的に下記の計算式によって計算を行います。
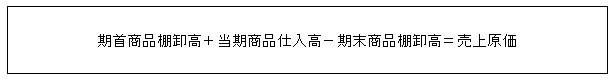
前期末の在庫(前期末の棚卸の金額)は、期首の在庫(期首商品棚卸高)となり、それに当期仕入金額を加算することで、販売可能な仕入金額の総額が計算されます。販売可能な仕入金額の総額から、期末の在庫(期末商品棚卸高)を控除すれば、当期中に無くなった商品の金額を求めることが可能になります。
盗難や紛失、自己使用などがないという前提なら、無くなった商品は、売れたから無くなったのだと仮定することができます。よって、実務上は、無くなった部分の金額を売上原価と考えて損益計算書を作成する場合があります。
つまり、棚卸をすることにより、売上原価を算定することが可能になるという側面があります。
棚卸をしないで売上原価を算定する方法
ちなみに、棚卸をしなくても、売上原価を算定することも可能です。具体的には、商品が売れる毎に、売れた商品の仕入金額(原価)を集計していけば、売上に対応する仕入金額である売上原価を算定することが可能となります。
何十年か前は、レジで全ての商品を登録することが難しく、期末に棚卸をして、初めて売上原価が計算できるという状態が当たり前でした。現在でも、レジに全ての商品を登録していない場合などは、棚卸を行わないと売上原価が計算できないということになります。
最近では、全商品をレジで管理して、売上の計上と同時に売れた商品を全て記録できるので、レジで売上原価を集計できてしまいます。この場合に、棚卸が不要かというと、そうではありません。なぜなら、売上に対応する売上原価を直接計算することは可能ですが、盗難や自己使用など売れていないけれども無くなっている商品について把握することができないからです。つまり、売上原価が算定できたとしても、本当に在庫が実在するかを確認するために、実地棚卸が必要になります。
実地棚卸の重要性
どのようなビジネスでも商品を扱っている場合には、定期的な実地棚卸は必須です。レジなどで売上原価を計算できない場合には、売上原価を計算する直接の手段となることは上に書いたとおりです。
また、レジで売上原価を計算できる場合でも、実際に、棚卸をすることで、盗難や従業員の不正によるロスが明らかになります。
例えば、小売店を複数店舗で経営しているような場合には、レジで計算されるあるべき在庫量と、実地棚卸で確認される在庫量で、一定規模のロスが集計されてきます。想定されるロスであれば、盗難であることが考えられますし、異常なロスが生じる場合には、従業員が不正をしているなどの可能性が考えられます。想定されるロスなのか、異常なロスなのかを把握する意味でも、定期的な実地棚卸は不可欠となります。また、ロスの金額が大きいようであれば防犯カメラの設置など、取るべき手段を検討することが可能になります。
真面目に帳簿を付けていても合わなくなるのが現金残高
現金出納帳を丁寧に記帳しているけれども、それでも現金が一致しないとか、レジの金額と現金残高が一致しないと言うことは、相当注意深く処理を行っていても起こります。人間のやっていることなので、どうしても釣り銭の間違いやレジの打ち間違いなどが起こりえます。また、記帳の漏れや間違いなども起こります。簿記の学習で、現金過不足という勘定科目が登場するのは、真面目に帳簿を付けていても合わないことが前提だからです。
定期的に実際残高と帳簿残高の一致を確認することが重要
現金の実際残高と帳簿残高のズレの原因としては、帳簿の付け方が間違っている場合や記帳漏れ、現金の受け渡しを誤ってしまった場合、不正が行われた場合などが想定できます。いずれも起きてはいけないことですから、防止する意味でも、実際の現金残高と帳簿上の現金残高を突き合わせることは実務上重要です。
では、どのくらいの頻度で、現金の実際残高と帳簿上の残高を突き合わせる必要があるかというと、例えば現金商売で現金が動く場合には、数時間ごとにレジにある現金残高とレジペーパー上の残高を合わせるという作業が行われています。また、金融機関などでは、毎日数字を合わせるという作業を行っているはずです。
あまり現金の動きがない会社でも、週に1回程度は、現金の実際残高と帳簿残高を突き合わせ作業を行うべきです。
現金出納を行う者と帳簿を付ける者を別にしたほうが良い理由
一般的には、現金の出納を行う人と、帳簿を付ける人を別けたが方が良いといいます。現金の出し入れと帳簿付けを同じ人が行う場合は、私的な領収書などを経費に紛れ込ませて、会社のお金を着服することが可能となってしまいます。ひどい場合には、偽の領収書などで多額の横領などが起こりうる可能性があるからです。
現金出納を行う人と帳簿を付ける人を別けておけば、少なくとも現金の引き出しをする際に他人のチェックが入ることになり、不正が起こりにくくなる効果があります。人員の確保自体にもコストがかかりますが、任せきりにする場合でも、第三者のチェックが入る仕組み作りが重要です。
適正な記帳が行われない場合のデメリット
税金の申告を行うためだけに、領収書だけ集めておいて、とりあえず帳簿を事後的に作るという実務も行われています。しかし、このような場合には、存在する資料でしか帳簿上の現金残高は作成されませんから、領収書のでない経費が漏れるなど、正しい計算結果は期待できません。
ひどい場合には、手元の現金が数万円しかないのに、帳簿上は数百万と計算されてしまうとか、現金残高がマイナスになってしまうなどという結果があります。もちろん、丁寧に原因を探していけば、ある程度は問題解決できる場合もありますが、完全に解決に至ることは少ないと考えられます。例えば、小さな横領などについては、発見されないという事態が起こりえます。
帳簿を正しく付けることは、税金の申告をする上でも必要ですが、会社の財産を守る意味でも重要です。会社のために正しく帳簿をつけましょう。
問題の所在
所得税基本通達34-1で、一時所得に該当するものとして、競馬の馬券の払戻金が例示されています。
通達は、法律ではなく、上級行政機関が下級行政機関に対して行う命令のことをいいます。つまり、課税当局は、通達がある以上、通達通りの処理をせざるをえないという状況があります。一方で、税金については、国民の財産権の侵害と表裏一体であるため、租税法律主義という基本的な考え方があります。簡単に説明すれば、法律に従ってのみ課税が行われるという意味です。
また、所得税法34条では、一時所得の計算をする上で、「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る」部分のみを、収入金額から控除できるとしています。つまり、外れ馬券は収入を生じた原因の発生に直接要した金額ではないから、所得の計算をする際に控除できないという取扱いになります。こちらは法律の規定ですから、一時所得該当すれば、外れ馬券は、所得を計算する際に控除できないという結論に繋がっていきます。
課税当局は、通達が存在する以上、一時所得としてしか処理はできませんし、一時所得である以上、外れ馬券は所得計算に際して控除できないという判断になります。
それに対して、納税者は、一時所得ではなく雑所得であり、所得の計算にあたって、間接的な経費である外れ馬券も必要経費として控除できると主張したわけです。
通達通りの処理を行った場合の問題点
さて、今回の外れ馬券の問題は、大きな問題点を内在しています。
報道によれば、3年間で28億7000万円の馬券を購入して、30億1000万円の払戻を受けたとされています。キャッシュで考えると、1億4000万円しか手元に残らないことになります。
ところが、一時所得に該当するとした場合、外れ馬券は経費とならないため、課税当局は5億7000万円の脱税をしたとして処理を行っています。
手元に1億4000万円しか残らないのに、5億7000万円の課税というのは、常識的に課税の仕組みがおかしいのではないかということを考えてしまいます。
一方で、30億以上稼いだ人が、28億円をギャンブルに使ったからといって、課税所得が減少することはありません。今回の事件と、どのようにバランスを取るのかということは非常に難しい問題です。
裁判所の判断と今後の課題
高裁判決では、「営利を目的とする継続的行為から得た所得」ということで、雑所得であるとして、外れ馬券を必要経費として認めました。
しかし、どの規模から雑所得になるのかという線引きを明確化する必要が生じます。例えば、今回のケースは28億円以上の馬券購入費用と30億円の払戻収入でしたが、2800万円の馬券購入費用と3000万円の払戻収入の場合は、どう判断すべきでしょうか。
今回のケースは特殊だという解説をよくみかけますが、類似の問題は、今後も起こりうるので、司法が外れ馬券の必要経費性を認めるのであれば、結果として立法上の手当が必要となってしまいます。
そもそも、今回の裁判では刑事事件と税務訴訟が並行して行われていますが、刑事事件については競馬の払戻収入について無申告であったことに端を発しています。この点について、大口払戻しに対する支払調書の提出など、所得が捕捉できるための仕組みについても手当が必要だという意見もあります。
そして、現時点での判決結果だけをみて、雑所得として申告するというのは、やめておきましょう。ちなみに、宝籤は非課税の制度が存在しています。制度を変更するとしても、ギャンブルだけ特別の枠を設けるのか、デリバティブなどの投機的な所得との境界をどうするのか、法人が馬券の購入を継続して行った場合にどうするかなど、簡単に答えがでにくい領域です。
判決の行方も含めて、税制が大きく動く可能性がある事件ですので、今後も注意していきましょう。
株主の種類
上場株式については、時価が存在するため、少数株主であって大株主であっても、市場で売却すれば同じ金額で売却できるので、どの株主でも基本的には、同じ時価であると考えられます。もちろん、大量保有している株主が、M&Aの際に有利に売り進めることができるなど、ケースによって状況が変わる場合もあります。
一方で、非上場の株式については、株式である以上、必ず換金できる保証はありません。そこで、配当を受け取ることができる権利か、あるいは、会社を支配することができる権利かという視点で、税法の世界では、株主を下記のようにグルーピングします。
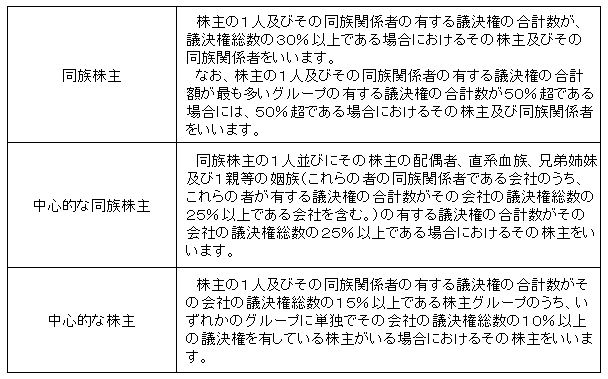
そして、現実には、上記にグルーピングされない、少数株主が存在します。
具体的な判定方法
(1)同族株主がいる会社
同族株主がいる会社は、同族株主は実質的な支配権を持つ可能性があるので、株式の議決権割合が5%以上の場合は、原則的な評価となります。また、議決権の5%未満となる場合でも、中心的な同族株主に該当する場合や、役員である場合は、原則的な評価となります。なお、同族株主の中に中心的な同族株主がいない場合には、5%未満の議決権の保有でも原則的な評価となります。
つまり、同族株主以外の場合は配当還元評価になるのはもちろんですが、中心的な同族株主がいる会社であれば、5%未満の議決権の保有であることを条件に、中心的な同族株主でなく、かつ、役員でない者は、配当還元評価が適用されることになります。
(2)同族株主がいない会社
非上場でも同族会社でない会社が存在します。同族会社でないので、同族株主は存在しないことになりますが、そのような場合は議決権割合の合計が15%以上のグループに属する場合は、その他の株主に比べて支配力を持つと考えて、原則的な評価となる場合があります。
議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主が、単独で議決権が5%以上となる場合には、その株主は原則的な評価となります。また、議決権が5%未満の場合でも、中心的な株主が存在しない場合、あるいは役員に該当する場合は、原則的な評価となります。
逆に、15%以上のグループに属する場合でも、中心的な株主がいる場合で、役員でもなく、自分自身の議決権が5%未満に該当する場合には、配当還元法による評価が適用されることになります。
実務上の留意点
実務では、もともと同族会社でない場合に、15%以上のグループを作らないような運営を行っているケースが散見されます。例えば20%の議決権を有したとしても、大株主ではあっても、現実的な支配権は有しません。それなら、15%未満の議決権として、低い評価での株式を保有している状態の方が、自分に相続があった場合などに、相続人に余分な税負担をさせずに済むことになります。
また、会社の運営とは無関係な状態でありながら、一定の割合議決権を持つ株主に相続があった場合は、遺産分割で5%未満の株主となるように遺産分割を行えば、同じ株式であっても事後的な対策として評価を下げることが可能です。また、相続人が少なく、5%未満株主にすることが遺産分割ではできないことが予測される場合には、遺言で、相続人以外が取得するように準備をしておくなどの方法も考えられます。
事業承継をする側からは、株式の分散はデメリットがあり、悩ましい話です。一方で、祖父が作った会社の株式を保有しているが、会社とは無関係の場所にいるような場合には、自分が保有する株式を分散させることで、相続人の相続税負担を軽くすることが可能です。
原則的評価方法と特例的評価方法
上場株式であれば、市場で売買されるため時価という概念が存在しますが、取引相場のない株式の評価については、取引自体がほとんど行われないため、純粋な意味での時価は存在しません。取引が行われない場合でも、相続税や贈与税を課税する必要があるため、財産評価基本通達で、評価方法を定め、その評価方法により計算された金額に対しての課税を行っています。しかし、ここで気をつけなければいけないのは、財産評価基本通達で計算された評価額は、厳密な意味での時価ではなく、課税を行うための便宜上の金額であるという点です。別の言い方をすると、フィクションの金額とも言えます。
事業承継の相続税対策を行うに当たっての基礎知識として、非上場の株式の評価については、原則的評価方法と特例的な評価方法である配当還元方式と呼ばれる方法があることを理解する必要があります。
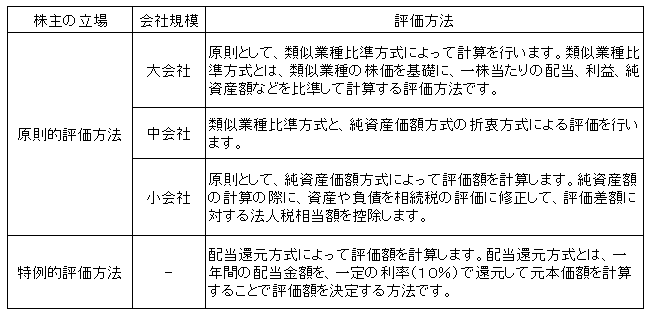
ここでは、細かい計算方法を理解することではなく、株主の立場によって、同じ会社の株式であっても、全く異なる評価方法が採用されることを理解頂ければと思います。また、同じ会社であっても、大会社に区分されるか小会社に区分されるかで、評価の方法そのものが変わってしまうという点です。つまり、相続税や贈与税の課税を行うための、価額の算定方法であり、その時点における時価を計算しようとしているわけではないのです。
株式分散の効果
事業承継対策で、株式を分散させることの効果は、同じ株式でも株主の立場によって評価額が変わることを利用したものです。例えば同族株主でも、持ち株割合を5%未満に抑えることで、特例的な評価方法である配当還元方式による評価となる場合があります。そこで、後継者には会社経営に最低限必要となる部分、例えば3分の2だけが相続されるようにしておき、それ以外の株式を遺言で少し離れた親族や、信頼できる従業員などが5%未満ずつ取得するようにするとの方法があります。株式の評価は取得者ごとに行うので、後継者が受け取った部分の株式は原則的評価によって評価されても、その他の取得者が取得する部分が配当還元評価になれば、相続税の節税効果があります。
因みに、原則的評価と配当還元評価で、同じ株式にも拘わらず、評価額について100倍以上の差が生じることもあり得ますので、それなりに大きな効果が期待できる場合があります。
株式分散のデメリット
株式を分散させることで、相続税対策に繋がるケースはありますが、デメリットについても考えておく必要があります。
懸念されるのは、少し離れた親族がいつまでも友好的かどうかは不明な点です。その後、相続が繰り返されることで、他人に近い状態になります。また、信頼できる従業員へ贈与したはずが、従業員の遺族に相続されたような場合は、ほとんど接点がない人が株主となってしまう点です。
議決権の3分の2を後継者が保有していれば、普通に会社を運営していく分には、たいていの場合は大きなトラブルにはなりません。しかし、M&Aなどのために、株式を買い集めるなどの必要が生じた際などに、苦労する可能性があります。
相続が繰り返されることで、音信不通の株主が生じるなどの問題や、株主と連絡が取れる場合も、株式を買い集めるのに金額面で折り合いが付かないというケースはよくあります。仮に相続税の計算のための評価は、配当還元法による評価であったとしても、それは相続税の計算のための評価額です。いざ、買取りを行おうとすると、非常に高額な金額での買取りを求められることも考えられます。
また、株式を買い集める必要がない場合でも、会計帳簿の閲覧請求権、株主総会の招集請求権、役員解任の訴えなど、少数株主の権利も決して軽視できるものではありません。関係がこじれてしまうと難しい問題が生じます。
相続税の税金という点に着目すると、株式の分散は魅力に感じますが、将来の不安定さとトラブルの原因を作らないということを考えると、株式の分散は得策ではないように思います。
事業承継税制の活用
ある程度の規模の会社で、内部留保も大きい会社の場合は、相続人が保有していた株式の評価が高く、事業を承継する相続人にとって、相続税が非常に重い負担になる可能性があります。そのような会社で、最低でも5年以上は事業を続けられることが確実に見込めるような場合には、事業承継税制の活用を検討することが最初にすべきことです。詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.tohoren.or.jp/zenkoku/index.asp?patten_cd=12&page_no=563
http://www.tohoren.or.jp/zenkoku/index.asp?patten_cd=12&page_no=568
要件を満たすか否か、手続が煩雑なこと、打ち切りになった場合などのリスクについても検討することが必要ですが、うまく適用できれば、株式の評価額の80%部分に対する相続税額が納税猶予され、免除される可能性があります。
もっとも中小企業者を対象としているので、大規模な会社は適用外であったり、逆に規模が小さすぎるとメリットが薄かったりと、思いの外ストライクゾーンが狭いという側面があり、なかなか利用に至らないケースが多いようです。
暦年の贈与制度を利用
毎年、株式の評価を行い、ある程度の贈与税を納めつつ、長期間にわたって株式を贈与しているケースはよく見聞きします。本人が、贈与税の申告をして納税していくと言うことは、本人に受贈の意識があることの裏付けになりますし、申告書を提出しておくことで贈与の事実を残しておけます。仮に10%の贈与税を負担したとしても、相続税で20%以上の税率となることが見込める場合には、株式の評価額が極端に低くなるなどの不測の事態がおこらない限りは、確実な節税手法と考えられます。
贈与税の負担がもったいないからということで、年間の贈与税の非課税枠の中で、贈与を繰り返し、法人税の申告の際に別表2の数字だけを動かしているようなケースも見受けられます。相続税の税務調査の現場では、名義預金がしばしば問題になりますが、名義預金と同じように、実際に贈与があったのか否かという部分から課税当局と見解が別れるリスクなどもあります。暦年の贈与制度を活用するのであれば、ある程度の贈与税の負担はリスク回避の上で不可欠です。そして、平成27年からは、直系尊属からの贈与税について、優遇されることになるので、相続税として予測される税率よりも贈与税率が低いのであれば、確実な節税に繋がります。地味ですが、基本的な節税対策と考えられます。
なお、相続時精算課税は、贈与時に課税はされなくても、相続税の申告を行う時点で、相続財産の計算に、贈与財産が組み込まれることになるので、相続税が課税されることが予測される場合の節税対策にはならないので、注意が必要です。
成り行きに合わせての対策
相続税の対策は重要ですが、想定外のことが起こってしまうと言う落とし穴があります。例えば、贈与税を支払いつつ相続対策をしていたところ、会社が立ちゆかなくなってしまって、結果として余分な税金となってしまうとか、後継者に株式を移転させてしまったところ、後継者が死亡してしまい相続税が多額に発生するなど、不測の事態が起こりえます。また、事業承継とは別な話で、相続対策で借入をしたら、借金だけが残ってしまったというような話しは、ありがちです。大きく動く対策には、それなりのリスクが生じます。
そこで、敢えて成り行きに合わせて対策を行うというのも、一つの方法です。例えば、会社の業績が下がり株式の評価が下がったところで、後継者へ株式を一気に贈与してしまうなどという手法です。
それ以外にも、自分が引退する際に役員退職金を多額に受け取るような場合は、退職金の支払により株式の評価が下がることが予測されます。その際に、株式を贈与してしまうというのも、よく利用される方法です。この場合は、代表者交代に伴って株式が移動するという点でも自然な流れです。
また、会社に資金が潤沢にあるようならば、後継者に株式を移動するのではなく、会社に株式を買い取って貰うなどの方法も考えられます。例えば、後継者が20%の議決権を有し、父が80%の議決権を有していた場合に、父が全ての株式について会社に買い取って貰えば、自動的に全ての議決権を子が持つことになります。また、会社が、一度に株式を買い取れないような場合に、毎年少しずつ買い取っていくなどの手法も考えられます。
事業承継対策は長期にわたって行うので、いろいろなやり方があります。個人的には、事業承継に関する相続税対策は、決め打ちで対策をするのではなく、いくつかの手法を用意しておき、成り行きに合わせて、複数の手法を組み合わせて、自然な形で行うのが好みです。
交際費の定額控除限度額の拡大
平成25年4月1日以降開始する事業年度から、中小法人については、支出する交際費のうち800万円を超える部分の金額が損金不算入という取扱いになりました。従来は、600万円までの90%が損金算入の上限でしたから、年間で200万円以上枠が増加したことになります。手書きで申告書を作成している場合は、古い別表を用いて計算をすると間違いが起こるので気をつけてください。
なお、ここでいう中小法人は、基本的には、資本金の額又は出資金の額が、1億円以下である法人(注1、注2)をいいます。
(注1)期末において、次に掲げる大法人との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人は除かれます。
- 資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人
- 相互会社
- 受託法人
(注2)完全支配関係がある複数の上記の大法人に発行済株式等の全部を保有されている普通法人についても除かれます。
生産性向上設備投資促進税制
産業競争力強化法が平成26年1月20日に施行されたため、平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアで、産業競争力強化法に該当するもののうち、一定規模以上のものの取得等をして、事業の用に供した場合は、特別償却と税額控除の選択適用が認められる制度です。
資産の詳細については、こちらを、ご覧ください。
http://www.tohoren.or.jp/zenkoku/index.asp?patten_cd=12&page_no=868
なお、3月決算法人で注意すべきは、平成26年1月20日から26年3月31日までの取得等の場合には、本制度の対象にはなるものの、実際に特別償却又は税額控除が行えるのは、平成26年4月1日を含む事業年度となることです。実質的には、この3月期に取得しても、特別償却は次年度からということになります。
所得拡大税制
所得拡大税制については、平成25年度税制改正で創設され、平成26年度税制改正で、要件の緩和と期限が延長されました。詳しくは下記をご覧ください。
http://www.tohoren.or.jp/zenkoku/index.asp?patten_cd=12&page_no=573
http://www.tohoren.or.jp/zenkoku/index.asp?patten_cd=12&page_no=865
所得拡大税制に関して、気をつけなければいけないのは、特段の準備がない場合でも、要件を満たせば適用できる点です。意識しないまま、要件を満たしてしまった場合などは、適用忘れが生ずる可能性があるので注意が必要です。
所得拡大税制の要件については、簡単には下記の3つです。
- 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が一定以上であること ⇒増加率が一定以上であること
- 雇用者給与等支給額が前年以上であること ⇒絶対額が増加していること
- 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること ⇒平均額で増加していること
本来であれば、要件緩和については、平成26年度税制改正であるため、平成26年4月1日以降開始事業年度から適用されるのが通例です。しかし、大綱にあったとおり、遡及して要件の緩和が行われることになりました。
ただし、平成26年3月決算の場合は、要件緩和前の要件で判定して旧基準を適用することになります。そして、平成26年3月期について、要件緩和前では要件を満たさない場合に、新基準で計算して要件を満たす場合は、平成27年3月期の法人税申告時に上積みして適用されることになりました。
なお、平成26年4月1日以降に終了する事業年度については、要件緩和後の取扱いで申告を行います。3月決算の場合だけ、特別という点については注意が必要です。
会計ソフトはバージョンアップが必要
一般的に利用されている会計ソフトは、バージョンアップさせないと、消費税率8%に対応しないようです。よって、会計ソフトを利用されている場合は、会計ソフトを最新の状態にバージョンアップをさせることをお勧めします。
会計ソフトをバージョンアップさせない場合は、下記のような問題が生じます。
(1) 消費税の計算が正しく行えない
多くの場合、消費税の計算の大部分を会計ソフトの機能に依存しています。例えば、税込108万円の取引があった場合に、本体価格100万円と、消費税部分8万円に区別するなどの作業です。仮に、消費税率が5%のままの会計ソフトを利用すると、108万円の取引について、本体部分を102万8,571円、消費税部分を5万1,429円と、誤った形で割り振ってしまうことになります。
(2) 貸借対照表や損益計算書が正しく表示されない
税抜き経理をしている場合は、消費税部分を外した金額で、貸借対照表や損益計算書を作成します。上記で示したように、消費税部分の金額を正しく抜き出すことができないので、結果として誤った貸借対照表や損益計算書が作成されることになります。
なお、税込経理を採用している場合は、貸借対照表や損益計算書の表示には影響を与えません。ただし、消費税の計算が正しく行われないという問題は残ります。
バージョンアップは早ければ早いほど良い
消費税率がアップされた現時点では、会計ソフトのバージョンアップは、早ければ早くしたほうが良いと考えられます。これは、4月になって入力されたデータが5%の消費税として入力されてしまうからです。後になって、消費税率引上げに対応した会計ソフトにバージョンアップしたとしても、5%で入力済みのデータが、自動的に8%に置き換わるわけではありません。
なぜなら、消費税の経過措置という取扱いがあり、4月以降でも、一部の取引については、消費税率が5%で据え置かれる場合もあるため、消費税率8%に対応済みの会計ソフトであっても、4月以降の取引については、5%と8%の消費税率が選択できるようになっているからです。
バージョンアップが遅れれば、入力済みのデータについて、5%から8%へ手作業で、税区分を変更する必要があるので、その作業の手間が増えることになります。
3月中に8%の税率を払う場合の処理
平成26年4月1日以降の消費税率が8%となりましたが、3月中の取引でも8%で請求が届くような場合があります。この場合、どのように処理したらよいでしょうか。
例えば、4月分の家賃について、3月中に支払うという契約は一般的です。仮に家賃が20万円だとした場合、3月分までは21万円の支払だったところが、4月分の家賃の支払は21万6千円になります。4月分の家賃を3月に振り込む際に、消費税率が8%だからといって、8%の税区分を選択したくても、多くの会計ソフトは3月の日付では8%としての入力ができない状態となっています。
そこで、実務上は、3月中は、いったん5%で入力しておいて、4月になった時点で8%に訂正するような振替仕訳を起こす必要があります。
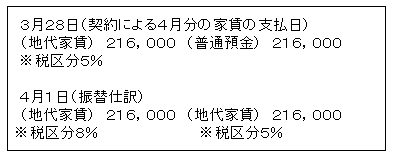
簿記の経験がある方は、理解しやすいと思いますが、5%の家賃を取り消して、8%の家賃に置き換える仕訳です。
実務上は、家賃だけではなく、3月と4月をまたいで保守料や警備料などの経費が生ずる場合に、前払の処理をしている場合には、4月分以降で8%の税率となっている部分については、振替仕訳が必要になってきます。
損失が生じた場合に他の所得と損益通算の対象となる所得
所得税の計算を行う際に、所得を10種類に分類して計算を行いますが、実際には10種類の所得について、全てをバラバラに計算を行うのでは無く、いくつかの所得については、合算して計算を行います。この場合に、所得の金額の計算上損失が生じた場合に、通算が行われるのは、下記の所得だけです。
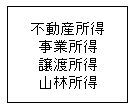
※これらの所得で損失が生じた場合、その損失を給与所得など他の所得金額から控除することができます。ただし、上記4つの所得以外、例えば給与所得で計算上損失が生じても、その損失を他の所得金額から控除することはできません。
なお、上記の4つの所得で損失が生じた場合でも、下記の取扱いがあります。
- 不動産所得の金額の計算上生じた金額のうち、(1)別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの、(2)土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額、(3)一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るものは、その損失がなかったものとみなされ、他の各所得金額から控除することはできません。
- 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できません。また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、株式等に係る譲渡所得等の金額と損益通算できません。
なお、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額がある場合に、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することは可能です。 - 申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額と損益通算できません。また逆に、先物取引に係る雑所得等以外の所得の損失も、先物取引に係る雑所得等の金額と損益通算できません。
- 譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失がある場合は、土地建物等の譲渡所得以外の所得の金額と損益通算はできません。また逆に、土地建物等の譲渡所得以外の所得の損失も、土地建物等の譲渡所得の金額と損益通算できません。
実務上は、アンダーラインを付した取引が非常に多く登場し、例外の方が日常的に多く見かけるという状況となっています。なお、ゴルフ会員権を譲渡した場合の損失についても、平成26年4月以降のものについては、損益通算ができない取扱いとなっています。
◆所得の合算と分離課税
所得税の計算は、所得の種類ごとに所得の計算を行い、その所得金額を合計して、総所得金額に対して、税額計算を行う総合課税が原則です。しかし、一定の所得については、他の所得と合計せず、分離して税額計算を行う分離課税という仕組みがあります。
分離課税の対象となるものは、下記の通りです。
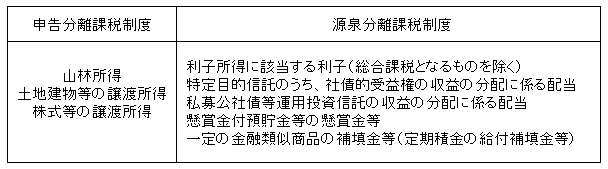
なお、退職所得については分離課税となりますが、退職所得の受給に関する申告書の提出があれば、源泉徴収で課税関係が終了し申告不要となりますし、退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合には、暫定的な額で源泉徴収を行い、確定申告を行って精算をすることになります。
◆損益通算と分離課税の適用関係
山林所得で損失が生じた場合、他の所得と通算することは可能だけれども、所得がプラスとなった場合は、分離課税であるため税額の計算を行う際に、他の所得と切り放して計算を行うということになります。
譲渡所得は、損失が生じた場合に損益通算が可能というのが、原則的な取扱いですが、実務上は株式や不動産の譲渡については、損失が生じた場合でも、損益通算が行えません。しかし、居住用資産を譲渡した場合の損失は、一定の要件を満たせば、他の所得と通算できます。つまり、例外の例外的な取扱いも多く登場します。
雑所得は、他の所得とは損益通算が行えませんが、雑所得内部での通算は可能であり、雑所得とされる売電収入で赤字があり、年金収入があるような場合には、雑所得内部での通算というケースも存在します。
なお、事業所得で生じた損失は、例えば給与所得と通算は可能と言うことになりますが、本当に事業所得なのか、あるいは、雑所得なのかについての判断が必要になります。なぜなら、雑所得で生じた損失なら、他の所得とは通算できない取扱いとなるからです。
所得税における所得区分
所得税では、所得区分を下記の通り10種類に分類しています。なぜなら、所得の種類によって担税力が異なるという前提で、所得の種類ごとに計算を行う必要があるからです。
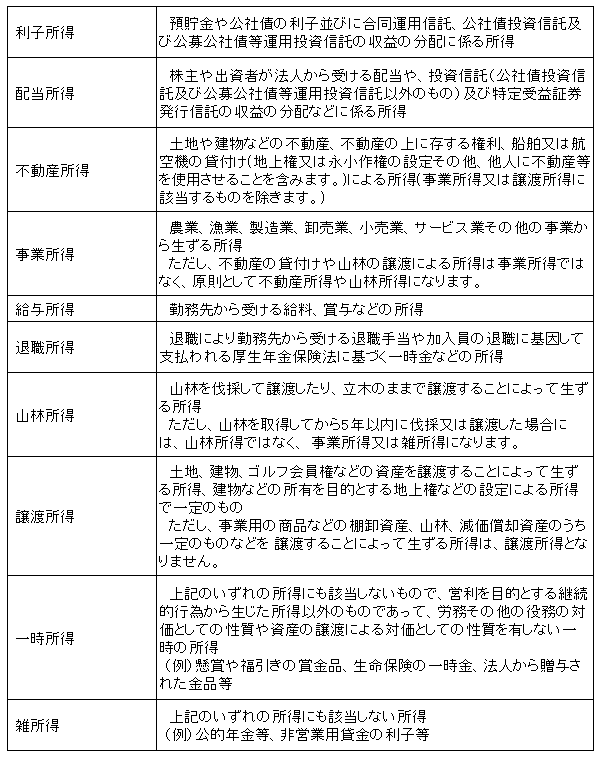
所得区分の重要性
今回は詳細に説明しませんが、複数の種類の所得を合算して税率を適用する総合課税と、他の所得と切り放して税率を適用する分離課税という課税方式があり、所得区分を適切に判断する必要があります。
さらに、ある所得が赤字となった場合に、他の所得と通算できるかという問題があります。例えば、給与所得がある場合に、太陽光発電設備を購入して赤字となった場合、給与所得と通算できるか否かという問題です。事業所得や不動産所得で赤字が生じた場合は、給与所得との通算が可能となります。一方で、雑所得で赤字が生じても、給与所得と通算することができないという仕組みとなっています。
太陽光発電設備の所得区分について
国税庁のホームページに掲載されている照会事例によれば、余剰電力の売電収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当し、給与所得者が太陽光発電設備を家事資産として使用し、その余剰電力を売却している場合には、雑所得に該当すると説明しています。
さらに、全量売電の場合でも、給与所得者が行っている場合は、それが事業として行われている場合を除き雑所得に該当するとしています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm
また、賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による売電収入については、余剰電力の売却収入は不動産所得に該当し、全量売電の場合は、不動産所得との関連が認められないことから、事業として行われている場合を除き、雑所得になるとしています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm
実務を行う上では、「事業として行われている」というのが、どの程度をいうのかという問題は残りますが、上記の照会事例で、大部分の売電については、所得区分が明らかになりました。
領収書等に係る印紙税の非課税枠が拡大
平成26年3月31日までに発行される「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された金額が3万円未満のものが非課税とされています。
平成26年4月1日以降に作成されるものは、受取金額が5万円未満のものについて、非課税とされることになりました。日常的に、3万円以上の領収書を発行している会社については、注意が必要です。
印紙については、誤って収入印紙を貼ったような場合に、過誤納となった文書の原本を提示することで、還付の手続が行えます。しかし、領収書については、多くの場合は、渡しきりになりますので、あとで気づいたからといって、領収書を渡した相手に、還付の手続をするので、返却してほしいとは、お願いできないことが想定されます。その意味では、取り返しのつかない間違いになるので、十分に配慮しておく必要があります。
なお、「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、受領事実を証明するために作成して、相手に交付する証拠証書です。例えば「領収書」は、典型的ですが、名称が「受取書」、「レシート」、「お買上票」であったとしても、金銭の受領事実を証明するために作成する場合は、「金銭又は有価証券の受取書」に該当します。
不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書の印紙税の軽減措置
従来から「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」については、軽減措置の対象となっていました。平成26年4月1日以後は、軽減措置が延長され、さらに拡充されることになります。具体的には、以下の表をご覧ください。

契約書の印紙については、契約書を作成する日が3月か4月かで、税額が変わります。3月までに契約しなくてよいのなら、4月に契約を交わす方が、微妙に有利です。
なお、誤って高い収入印紙を貼ってしまったことに気づいた場合は、過誤納となった文書の原本を提示することで、還付の手続が行えます。
消費税と金額判定の関係
領収書の場合でも、契約書の場合でも、金額によって、印紙税の金額が異なってきます。印紙税の金額を判断する際に、消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合には、その金額を含めないところで、金額の判定を行うことになります。
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/140121/pdf/01.pdf
3月に出荷された商品が4月に入荷された場合の取扱い(26年1月Q&A問1)
4月以降の消費税率は8%になります。しかし、実務上は微妙な問題点があります。例えば、販売する側が3月31日に出荷した場合で、購入する側には4月1日到着するというケースです。
実務的には、売上を計上する側は、出荷した日付で売上を計上する場合か、購入側の検収を待って売上に計上する場合の2パターンの処理方法が考えられます。一方で、仕入を行う側では、入荷をした日付で仕入を計上するか、検収が完了した日付で仕入を計上する方法が考えられます。会計処理としては、いずれの方法をとることも、継続適用を前提として、会社が任意に決めてよい取扱いとなっています。
この場合に、売り主が出荷基準を採用していた場合、3月に出荷すれば3月の売上として、消費税率は5%となります。一方で、買い主が入荷基準を採用していれば、商品の到着が4月1日であれば、4月1日の仕入として、消費税率は8%になるのではないかという疑問が生じます。日本の消費税法はインボイス方式を採用していないので、このような売り主と買い主で泣き別れの処理になることも認められるのでないかとの考え方もあり、専門書などでも、異なる結論が紹介されるなど混乱が起きている状態でした。
平成26年1月公表のQ&Aの問1で、このような場合は、売り主が5%の消費税率で販売したのだから、買い主も5%の消費税の処理をするという、極めてシンプルで理解しやすい回答を公表しました。実務的には、相手の請求書に合わせて処理をすれば、基本的には正しい処理が行えるようになりました。
契約上3月に支払われる4月分の家賃の消費税率(平成26年1月Q&A問6)
資産の貸付けについては、その収益の計上の時期について、所得税の基本通達で下記のような取扱いがあります。
不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に、掲げる日によるものとする。
(1)契約又は習慣により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払いを受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
上記アンダーライン部分のように、契約で支払日が定められているものについては、支払日に収入を計上するという取扱いとされています。この取扱いにしたがって、4月分の家賃は3月の収入金額に計上すべき家賃なので、旧税率の5%になるのではないかとの疑問が生じていました。
しかし、この点についても平成26年1月公表のQ&A問6で、4月分なら新税率の8%を適用し、逆に支払うべき日が後払いの契約で3月分の家賃を4月に支払うという場合は、4月に支払われたとしても3月分の家賃なので旧税率の5%とするとの結論となりました。
上記の問題は、いずれも条文や通達を丁寧に読むと疑問が生ずる箇所であり、専門家の間でも疑問が呈されていました。しかし、消費税の税率については、お客さんとの金額の話しですから、経営者が現場でリアルタイムに解決する必要がある問題でした。その意味では、平成26年1月公表のQ&Aは、一般の方に理解しやすい内容となっており、多くの方が読んでおくべき内容です。
所得税関係
所得税関係では、今年の4月からゴルフ会員権等の譲渡損の損益通算禁止、平成27年から最高税率の引き上げ、平成28年からは金融所得に対する改正などが気をつけるべき改正内容が盛りだくさんです。
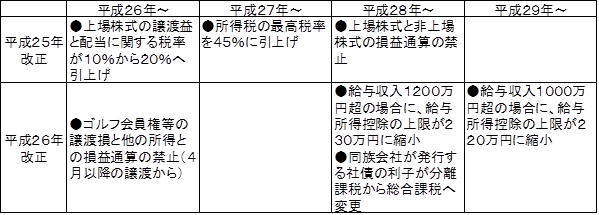
法人税関係
法人税関係では、産業競争力強化法が平成26年1月20日施行され、生産性向上設備投資促進税制について、平成26年1月20日以降取得分から適用される事になった他、交際費制度の改正、復興法人税の1年前倒しでの廃止、所得拡大税制の要件緩和など、法人にとっては朗報となる改正が多くあります。
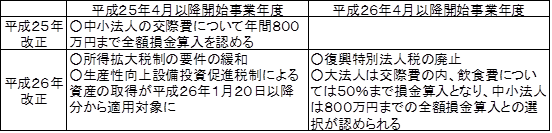
相続税・贈与税関係
相続税関係では、平成27年から基礎控除の縮小など相続税の対象となる納税者が増加する一方で、小規模宅地の評価減制度、相続時精算課税制度の要件緩和、事業承継税制の要件緩和など、大きな改正が行われています。
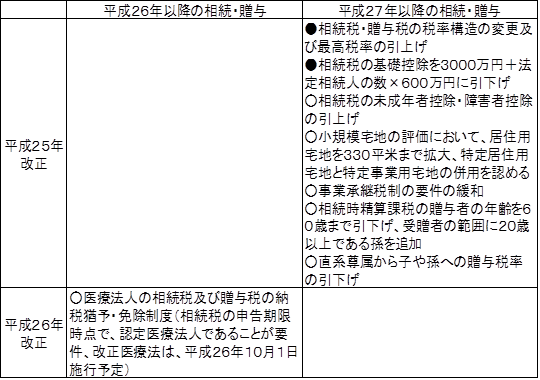
消費税関係
消費税については、消費税率の引上げが非常に大きな改正です。レジの切替、店内での掲示の変更、金額の変更などやるべきことがたくさんあります。
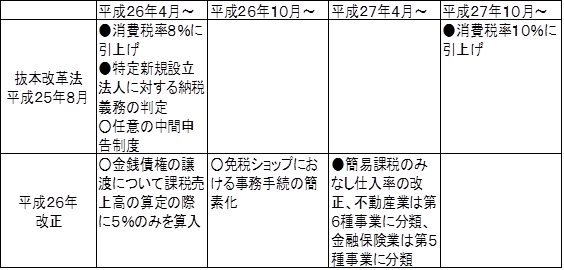
金銭債権譲渡にも5%特例の導入
消費税の計算の仕組みは、預かった消費税と、支払った消費税の差額を納税するというものです。しかし、支払った消費税の全額について控除できるわけではなく、課税売上の割合に応じて、控除できる金額が変わってくる仕組みになっています。
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.tohoren.or.jp/zenkoku/index.asp?patten_cd=12&page_no=599
結果として、非課税売上の割合が高いと、仕入税額控除できる消費税が減少して、消費税の納税額が増加する仕組みになっています。課税売上の割合を計算する際に、有価証券の譲渡については、譲渡金額の5%部分のみ計算に反映させるという特例が、消費税が創設された当初から存在しました。
消費税が導入されて20年以上が経過し、有価証券の譲渡のみについて特例とすることが、経済環境にそぐわない状況に変化してきました。近年の経済状況下においては、住宅ローンの証券化、企業再生支援に伴うファンドへの売却など、有価証券だけでなく、金銭債権の売買が一般化しており、円滑な金銭債権の譲渡が行えるような環境作りへの期待が高まってきていました。
平成26年度税制改正で、消費税の課税売上割合の計算を行う際に、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を、課税売上割合を計算の際の分母となる資産の譲渡等の対価の額に算入することに改正が行われます。
なお、この改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡から適用されます。
免税ショップの事務手続きに関する改正
外国人旅行者の訪日動機として、ショッピングの期待が高く、外国人旅行消費額全体の30%をショッピングが占めています。しかし、外国人旅行者が日本で購入した物品の購入率が上位となっている食品類、飲料類、化粧品類、薬品類等が免税対象品目から除外されていました。また、免税手続に時間がかかり、外国人旅行者の利便性を損ねているという問題点がありました。
外国人旅行者のショッピングにおける利便性を向上させ、日本における旅行消費を増加させるために、全ての品目を免税対象とするとともに、免税手続を簡素化することとしました。
なお、下記の改正はいずれも平成26年10月1日以後に行われる取引から適用されます。
- 従来は、食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類並びにフィルム、電池その他の消耗品については、免税対象外物品とされていました。平成26年度改正で、一定の方法で販売することを前提に、免税販売の対象物品に消耗品を追加します。
- 購入記録票等の様式の弾力化及び手続きの簡素化が行われます。
- 1人の旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する免税対象物品(消耗品以外の品物)の額が100万円を超える場合には、輸出物品販売場を経営する事業者が保存しなければならない書類に、その旅行者の旅券等の写しが追加されることになります。
(1)改正の経緯
従来から、簡易課税を利用する場合に益税が生ずる可能性がある点について、問題視されてきました。本来は、事務の簡素化を認める制度であるはずが、事務の簡素化に加えて益税までもたらす可能性があるからです。
平成元年4月に消費税が導入された当時は、適用上限が基準期間の課税売上高5億円以下で、事業区分も第1種事業と第2種事業のみと、本当に簡易な制度としてスタートしました。しかし、益税に対する批判を浴び、幾多の改正を経て、現在は、基準期間の課税売上高5000万円以下まで適用事業者を絞り込み、さらに益税が生じないように、事業区分は第1種事業から第5種事業までに細分化しています。
消費税率引上げについて、平成24年8月に改正法が公布され、平成24年10月に会計検査院報告書で簡易課税の益税の問題は解決されていないとする報告がなされていたのが、今回の改正に繋がっています。
(2)改正の内容
今回の改正では、従来の5種類の事業区分から、6種類の事業区分に変更されます。また、従来は第4種事業とされていた金融業及び保険業を第5種事業とし、従来は第5種事業とされていた不動産業を第6種事業と分類することになりました。
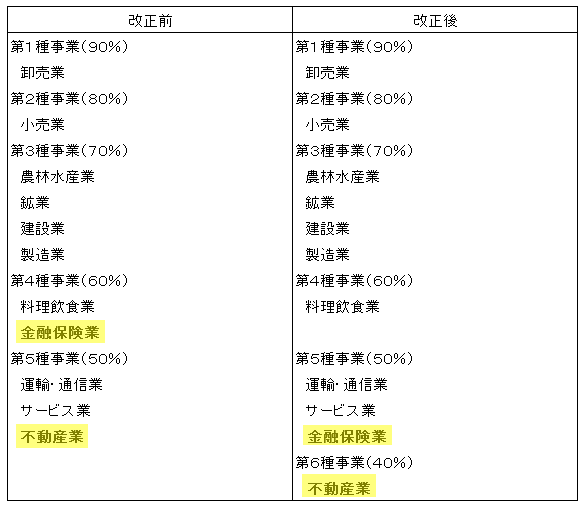
(3)適用開始時期とその対策
簡易課税のみなし仕入率の改正については、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されることになります。
今回の改正により、従来は簡易課税を選択することで有利になっていた事業者が、簡易課税を選択することで不利になるケースも考えられます。簡易課税の適用をやめる場合は、適用をやめようとする事業年度が開始する前に、簡易課税制度選択不適用届出書を提出する必要があります。事業区分が変更になる、金融保険業、不動産業については、有利不利の検討を改めて行っておく必要があります。
また、今回は改正とは直接関係がないそれ以外の業種についても、簡易課税を利用することによる有利不利のチェックは定期的に行いましょう。
なお、簡易課税については、下記をご覧ください。
http://www.tohoren.or.jp/zenkoku/index.asp?patten_cd=12&page_no=596
給与所得控除の上限の引下げ
平成24年度税制改正で、給与所得控除の上限が設定され、平成25年分の所得税から給与収入が1500万円を超える場合には、給与所得控除額が245万円で定額となりました。この改正で、給与所得控除の問題点については、一段落ではないかと思われていたのですが、平成26年度税制改正で、更なる改正が行われました。
改正の内容は、下記の通りで平成29年分の所得税からは、給与収入が1000万円を超えると、給与所得控除が220万円で打ち止めとなってしまうというものです。
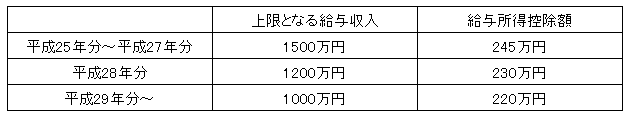
課税所得が900万円超で1800万円以下の所得税率は33%、住民税の税率が10%ですから、仮に1500万円を超える給与収入がある場合には、平成29年以降は、給与所得控除が25万円減少して、年間で107,500円の税負担の増加が生じることになります。
地味な改正ですが、多くの人に影響を与える改正です。
ゴルフ会員権売却による節税に蓋
ゴルフ会員権を売却した場合の損失を、給与所得など他の所得と通算することで、所得税の節税が可能でした。この点については、随分前から、毎年のように税制改正の時期になると議論されてきました。
平成26年度税制改正で、平成26年4月以降のゴルフ会員権の売却によって生じた譲渡損は、他の所得との通算ができなくなりました。
従来から所得税法では、生活に通常必要でない資産に係る所得の計算上生じた損失について、損益通算をできないこととしていました。損益通算できないものの具体例としては、競走馬、美術品、別荘などがありましたが、今回の改正で、ゴルフ会員権やリゾート会員権を、生活に通常必要でない資産に含めることになりました。
なお、平成26年3月までの、売却であれば、他の所得と通算することが認められます。含み損のあるゴルフ会員権を保有している場合は、最後の節税のチャンスです。是非、ご検討ください。
少人数私募債の利子を利用した節税に蓋
所得税は、累進税率であるため、高額所得者は累進税率の対象とならない分離課税となる所得を増やすことで節税をすることが可能です。そこで、自分の経営している会社に、少人数私募債などを発行させ、経営陣が引き受け利子を受け取るなどの手法が利用されてきました。
今回の改正で、平成28年分からは、同族会社が発行する社債の利息については、総合課税の対象となり累進税率が適用されることになりました。分離課税で20%だった税率が、累進税率の適用で最大55%まで跳ね上がります(厳密には、復興特別所得税が上乗せされます)。
1.医業継続税制の概要
持分のある医療法人の出資者に相続があった場合に、その相続税の申告期限において、医療法人が認定医療法人であれば、相続により取得した出資持分に係る相続税が移行計画の期間終了時まで猶予される制度です。
また、移行期間中に、相続人が持分の全てを放棄し、かつ、その医療法人が持分ありの医療法人から持分無しの医療法人に移行した場合は、その相続税が免除されます。
なお、複数の相続人がいるような場合に、出資持分の放棄について、タイミングのずれが生じると、最初に持分を放棄した者から、残りの出資持分を有する者へ、出資持分の価値の増加に対する贈与税が課税されます。それでは、持分なしの医療法人への移行の足かせとなってしまいますから、他の相続人の持分放棄により課税されるはずの贈与税について、納税猶予を認め、やはり持分なしの医療法人へ移行が完了すれば、その猶予税額を免除するという仕組みになっています。
2.認定医療法人について
税制改正大綱によれば、「認定医療法人」とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画について、認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人を言います。
なお、新しい医療法自体が、平成26年4月以降に施行される予定のものであり、名称等の変更の可能性がありますが、出資持分のある医療法人が、出資持分のない医療法人へ移行するための移行計画について、厚生労働省が認定する仕組みとなっています。
平成18年の医療法の改正により、現在は出資持分のない医療法人しか設立することができません。しかし、現存する医療法人の大半は出資持分のある医療法人となっており、平成18年改正によれば、いずれは出資持分のない医療法人へ移行しなければならない前提となっています。
今回の改正は、出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人へ移行がスムーズに行われるように、移行計画について認定を受けている場合には、相続税を猶予し、計画通り、出資持分のない医療法人へ移行した場合には、相続税を免除するというものです。
なお、認定を受けられる期間は、認定制度の施行の日から3年以内であり、移行期間は認定を受けてから3年間となることが予測されています。
3.出資持分のない医療法人へ移行する際の問題点
出資持分のない医療法人であれば、そもそも出資持分が存在しないため相続税の対象となりません。
しかし、出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人に移行する際に、出資持分を放棄するタイミングがバラバラだと、出資持分を最後まで有する個人に贈与税が課税されるという問題がありました。本改正では、この点についての問題点は解消されました。
また、もう一つの問題点として、相続税法66条の4の規定にある、法人に対する贈与税の問題が生じるかもしれないというリスクがあります。あくまでも、特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときに、課税される仕組みですが、今回の大綱をみている限り、この部分についての取扱いについては、変更はありません。十分な検討が必要です。
同じように持分のない医療法人である社会医療法人は、ハードルが少し高いので、長期的に持分のない医療法人へ移行することを検討していたような場合には、朗報と言えるでしょう。
中小企業向けの交際費の取扱いは2年間延長
昨年は、中小法人の交際費について、800万円以下の部分はその全額について損金算入するという改正が行われました。詳細については、下記をご覧ください。
昨年の改正も、かなりインパクトがある改正でしたが、租税特別措置法であることから、従来の期限を引き継ぎ1年限りとの扱いでした。平成26年度税制改正で、この取扱いが2年間延長されることとなり、当面はこの取扱いが存続されることが期待できます。
多くの中小企業では、年間800万円の交際費をフルに利用することはないため、交際費の損金算入が実質全面的に認められるようになったと考える事もできます。
大法人に対する交際費規制の問題点
昨年の改正で、中小法人に対して、交際費の損金算入枠が拡充されました。大法人についても、消費の拡大を通じた経済の活性化の観点から、交際費の損金算入を認めるべきではないかとの検討がなされてきました。
ちなみに、大法人とは資本金1億円超の法人をいいます。また、資本金等が5億円以上の法人等の100%子会社の場合は大法人と同じように扱われ、交際費の全額について損金不算入とされてきました。
ただし、大法人といっても、資本金1億円を少し超える法人もあれば、資本金100億円以上の法人も500社以上も存在します。仮に、資本金100億円以上の法人に対して、年間800万までの交際費の損金算入を認めたとしても、ほとんど影響がない可能性があります。その意味では、どのような手法で大法人に交際費の損金算入を認めるのかについては、気になるところでした。
飲食のための支出について50%を損金算入可能に!
経済の活性化という観点から、平成26年度税制改正では、大法人であっても、飲食のための支出については、50%の損金算入を認めるという計算方法を採用しました。なお、飲食のための支出でも、社内接待費は除くこととされていますので、注意が必要です。
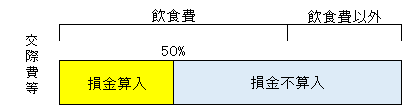
経済の活性化という観点から、平成26年度税制改正では、大法人であっても、飲食のための支出については、50%の損金算入を認めるという計算方法を採用しました。なお、飲食のための支出でも、社内接待費は除くこととされていますので、注意が必要です。
なお、支出交際費等のうち、飲食費の50%までを損金算入を認めるという内容ですから、金額的な制限はなく、交際費のうち3,000万円が飲食にかかるものであれば、1,500万円について損金算入が認められることになります。
なお、資本金の額が1億円以下で税法上は中小法人に該当するけれども、売上高の規模は大きく、飲食にかかる交際費を年間で1,600万円以上使用する会社も想定されます。そこで、中小法人については、800万円の定額控除と、飲食費の50%損金算入と比較して有利な方を選択適用することが認められています。
法人税関係
秋に公表された「民間投資活性化等のための税制改正大綱」で、設備投資の促進、所得拡大税制など、影響が大きい改正項目が先行して公表されていました。
年末の大綱で注目度が高いのは、大企業でも交際費の一部が損金算入できるという取扱いです。交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の50%について損金算入が認められるようになります。
また、ニュース等で注目されていた復興特別法人税は1年前倒しで廃止されることになりました。
所得税関係
ゴルフ会員権を譲渡した場合に他の所得と損益通算できるという取扱いが、平成26年4月1日以後の譲渡から認められなくなります。ここ数年、毎年のように改正されるとの噂があった項目です。損益通算を利用するために、駆け込みでの販売が急増する可能性があります。
昨年の改正で給与収入が1500万円以上の人について、給与所得控除の上限が定められました。これについて、漸次引き下げを行い、最終的には給与収入1000万円以上の人は、給与所得控除が220万円で打ち止めとなることなりました。地味ですが、多くの人に影響する改正です。
少人数私募債を発行して、その利子が分離課税となることを利用する節税手法が存在しました。しかし、平成28年からは、総合課税されることになり、同族会社が発行する社債を利用した節税手法が使えなくなりました。
相続税関係
個人が医療法人の持分を相続などで取得した場合に、その医療法人が認定医療法人(仮称)であるときに、納税猶予及び猶予税額の免除を認める制度です。医療法人に関する相続税対策が、大きく変わる可能性があります。また、相続税だけではなく、贈与税についても、医療法人の持分について特例が用意されます。医業継続に係る納税猶予制度と一括りにすることができます。
消費税関係
簡易課税のみなし仕入率が、従来の5段階から6段階に変更されることになりました。金融業及び保険業は第5種事業となり、みなし仕入率が60%から50%になります。また、不動産業は第6種事業に分類されることになり、みなし仕入率は50%から40%に引き下げられます。平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されることになります。みなし仕入率が変更される業種については、有利不利に関して再検討が必要です。
消費税率の引上げに伴って、軽減税率が導入されるか否かについて非常に注目されていました。しかし、10%時に導入すると大綱に記載されたに留まりました。10%導入時にとは記載されていないので、どの時点で軽減税率が導入されるのかについては、白紙に近い状態と考える事ができます。
国際課税
外国法人に対する課税の考え方を、「総合主義」から「帰属主義」に見直すことになりました。OECD加盟国のほぼ全てで、帰属主義が採用されているので、グローバルスタンダードに準拠することにしました。
この改正により、国際間で二重課税される部分が減少すると共に、課税の空白が減少することが期待されています。
1.転嫁対策特別措置法の概要
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」という長い名前の法律が、平成25年6月5日に成立し、平成25年10月1日より施行されています。なお、法律名が長いので、転嫁対策特別措置法と省略して説明を行います。概要としては下記の四つの内容となっています。
- 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
- 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
- 価格の表示に関する特別措置
- 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
2.消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
平成26年4月以降の商品の仕入などについて、消費税の転嫁を拒む行為が禁止されます。規制対象となるのは以下の通りです。現実的には、資本金3億円以下の事業者あるいは個人事業者と継続的に取引を行っている法人事業者が該当するので、ほとんどの法人は規制対象になると考える事ができます。
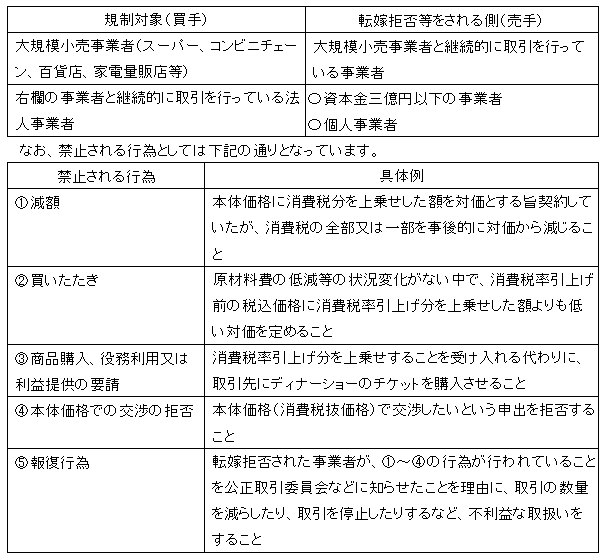
違反行為があると認められる場合には、公正取引委員会が勧告を行い、その旨を公表されることになります。企業イメージの毀損に繋がりますので、注意が必要です。転嫁対策特別措置法の存在を知らないで、消費税の引上げ分を値引きするように取引先に要請してしまっては大変なことになりますので、十分に社員教育を行っておくことが重要となります。
3.消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
消費税率が3%から5%へ引上げられた際に、消費税還元セールと銘打った商戦が展開されましたが、そのような宣伝や広告を行うことが禁止されます。
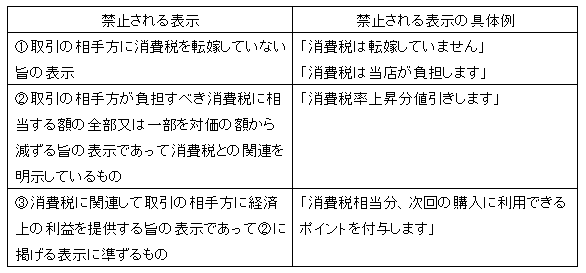
消費税率が3%から5%へ引上げられた際に、消費税還元セールと銘打った商戦が展開されましたが、そのような宣伝や広告を行うことが禁止されます。
これらについても、商売に熱心なあまりから、転嫁対策特別措置法の存在を知らずに、うっかりと実施してしまう可能性が想定されます。違反があった場合、その旨が公表される可能性があるので注意が必要です。こちらの違反については懇意にしている取引先からではなく、競業相手である同業他社から通報されることも十分に考えられます。広告を出す際には抵触しないように十分な検討が必要です。
4.価格の表示に関する特別措置
(1)税抜き表示について
本来は、小売り段階では税込表示が強制されます。しかし、税込で表示した値札について、平成26年4月1日に一斉に付け替えるなどの作業は大きな負担になります。また、税込金額を印字した商品なども多く見られ、税率5%の金額が印字された商品について、平成26年4月1日以降に、値段のシールを上から貼るなどの負担が生じることになります。そこで、平成25年10月1日以降、事業者の値札の貼り替えなどの事務負担への配慮の観点から、表示価格が税込であると誤認されないための措置を講じていれば、税込価格を表示しなくても良いという特例が設けられています。ただし、できるだけ速やかに、税込表示するように努めなければならないとされています。
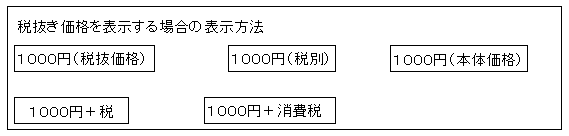
上記のように、税抜価格であることが明示される表示をすることが認められます。また、商品には税抜価格のみを表示しておいて、「当店の価格は税抜き表示となっています。」と、消費者が商品を選択する際に目に付きやすい場所に明瞭に表示する形も認められます。
(2)税込の金額が印字されている場合の対応方法
また、商品に税込表示が印刷されている場合などで、すべての商品について値札を貼り替えることが困難な場合は、「旧税率(5%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。」と商品を選択する際に目に付きやすい場所に表示するなどの対応を行う必要があります。
(3)税込価格が明瞭に表示されているか否かについて
事業者が、税込価格に合わせて、税抜価格を表示する場合において、税込価格が明瞭に表示されていれば、景品表示法の不当表示は適用しないこととされています。
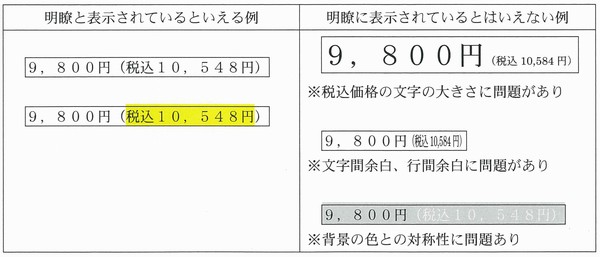
5.消費税の転嫁及び表示の方法の決定に関する共同行為に関する特別措置
事業者等が行う転嫁カルテル及び表示カルテルについて、公正取引員会への事前の届出を行うことで、独占禁止法の適用除外となります。
なお、認められるのは、①消費税分を上乗せするか否か、②消費税の端数処理についてどうするかの転嫁カルテルと、消費税の税率引上げ後の表示方法の決定に関する表示カルテルです。なお、転嫁カルテルについては、参加事業者の3分の2以上が中小事業者であることが必要です。
なお、本体価格を統一することは当然に認められませんので注意が必要です。認められるのは、消費税の転嫁の方法と表示の方法に関してです。
収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革の促進
(1)事業再編を促進するための税制
青色申告法人で産業競争力強化法施行の日から平成29年3月31日までの間に、産業競争力強化法における特定事業再編計画について認定を受けたものが、特定事業再編計画に記載された、特定事業再編により特定会社の株式等を取得し、かつ、その株式を事業年度終了の日まで引き続き有している場合に、その株式の取得価額の70%までを「特定事業再編投資損失準備金」として積み立てることで、損金算入を認めるという内容です。
この準備金は積立期間終了の日を含む事業年度の翌事業年度から5年間で均等額ずつ益金算入することになります。そして、積立期間は、法人が特定事業再編計画について認定を受けた日から10年を経過する日若しくは、特定会社が3年連続で営業利益を計上した場合の事業年度終了の日のいずれか早い日までの期間となります。
準備金の積立で、損金算入が認められようになるのは、平成26年4月1日以後に終了する事業年度であり、仮に産業競争力強化法施行の日から平成26年3月31日までの間に、特定株式を取得した場合には、平成26年4月1日を含む事業年度に損金算入が認められます。
(2)事業再編等に係る登録免許税の軽減
産業競争力強化法に規定する事業再編計画、特定事業再編計画又は中小企業承継事業再生計画の認定を受けた認定事業者等が、これらの計画に基づき、株式会社を設立する場合、増資、組織再編などの際の登記に対する登録免許税が、以下のように軽減されます。なお、この軽減措置が受けられるのは、各種計画の認定を平成28年3月31日までに受けた場合に限定されます。
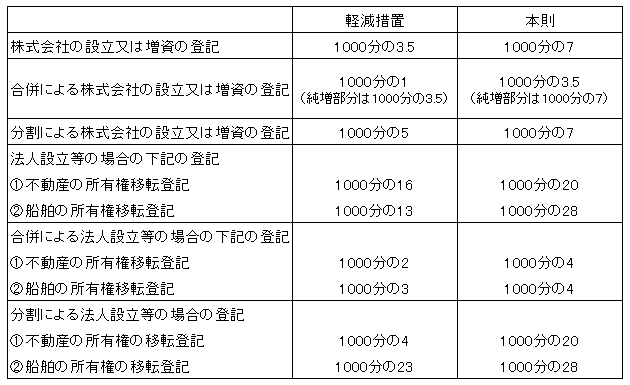
◆設備投資に関する税制
(1)既存建物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設
青色申告書を提出する法人が、耐震改修対象建築物を、平成27年3月31日までに「建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断結果の報告を行ない、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修により取得し、又は建設したその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却が認められます。なお、本制度は法人だけでなく、青色申告を行う個人事業者にも認められる制度です。
取得時期については、平成26年4月1日から、耐震診断結果の報告を行った日以後5年を経過する日までとされています。
耐震改修対象建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律の既存耐震不適格建築物のうち耐震診断結果の報告が同法の規定によって義務付けられるものをいいます。
耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替であって、その耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合することになるものとして、地方公共団体の長、指定確認検査機関、建築士による証明がなされたものをいいます。
(2)固定資産税の減額
下記の資産の取得等について、固定資産税が減額される取扱いがあります。該当資産を取得する可能性がある場合は気にしておくとよいでしょう。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された家屋について、政府の補助を受けて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った場合で、その旨を市町村に申告した場合
- 浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が、水防法に規定する浸水防止計画に基づき、浸水の防止を図るために取得する償却資産
- ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の冷凍・冷蔵機器)
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律における一定の基準適合表示の付された特定特殊自動車
ベンチャー投資促進税制の概要
産業競争力強化法の施行日から平成29年3月31日まので間に、産業競争力強化法に規定する特定新事業開拓投資事業計画について認定を受けた投資事業有限責任組合に係る投資事業有限責任組合契約を締結しているものが、その認定を受けた日以後にその投資事業有限責任組合に出資をし、認定を受けた日から投資事業有限責任組合の存続期間終了の日までの期間内において、特定新事業開拓投資事業計画に従ってその投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓者の株式を取得した場合において、その簿価の合計額の80%までについて「新事業開拓事業者投資損失準備金」として積み立てることで、損金算入を認めるという内容です。
簡単に言えば、要件を満たすファンドへ投資をした場合に、投資額の8割について損金算入できるという内容です。
つまり、新事業を始める事業者、そのようなファンドを組成する事業者、手元資金に余裕があり課税の繰延をしたい法人、三者三様にメリットがある制度と言えます。もちろん、投資する側は、新事業への投資を行うわけですから、投資に関するリスクはありますが、そのリスク部分について先取りできる点で、改正前に比べて積極的に取り組める環境が整ったと言えるでしょう。
ベンチャー投資促進税制の対象者と適用対象期間
特定新事業開拓投資事業計画について認定を受けた投資事業有限責任組合に係る契約を締結しているものは、その組合の有限責任組合員に限られます。また、その法人が適格機関投資家である場合には、その組合に対する出資予定額が2億円以上である場合に限られます。
なお、適格機関投資家とは、この制度にかかる投資事業有限責任組合契約を締結した日を含む事業年度の開始の時に、その他有価証券である株式等の簿価が20億円以上の者をいいます。
本制度の投資を行うタイミングは、平成26年3月31日以前ということも想定されますが、新事業開拓事業者投資損失準備金として積立て、損金算入が可能となるのは、平成26年4月1日以後に終了する事業年度からとなります。
創業促進のための登録免許税の軽減
ベンチャー投資への促進税制とは、全く異なる内容ですが、創業促進のために一定の要件を満たす法人設立については、設立に要する登録免許税を軽減する措置が導入されます。
個人が、産業競争力強化法に規定する認定創業支援事業計画に係る認定を受けた市区町村で、認定創業支援事業計画に記載された特定創業支援による支援を受けて株式会社を設立する場合は、その設立にかかる登録免許税が軽減されます。
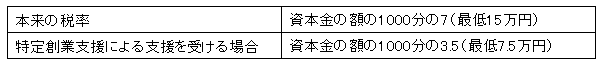
なお、上記の軽減措置は、産業競争力強化法が施行されてから、平成28年3月31日までに登記申請をする場合に適用されます。
生産性向上設備投資促進税制
前回、ご紹介した生産性向上設備投資促進税制ですが、中小企業等に向けて先端設備については適用資産の範囲を広くし、また、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備における生産性の向上の要件が緩和されています。具体的には下記の内容です。
(1) 中小企業等にのみ認められる先端設備
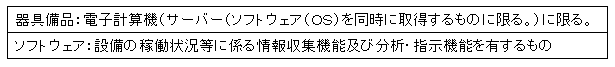
(2) 中小企業等に認められる生産性向上の要件の緩和
生産ラインやオペレーションの改善に資する設備とは、生産性の向上に係る要件を満たすことにつき経済産業局の確認を受けた設備計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアをいいます。この生産性の向上に関する要件は、投資計画に対する投資利益率が15%以上であることが、本来の要件となっていますが、中小企業等の場合は投資利益率が5%以上で良いとされています。
中小企業投資促進税制の延長と拡充
一般に中小企業投資促進税制と呼ばれる、中小企業者等が機械を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、より充実した制度とした上で、適用期限を3年間延長することになりました。
中小企業者等が、産業競争力強化法の施行日から平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものについて、即時償却が認められることになります。従来は、30%の特別償却だったものが、取得価額の全額について即時償却が可能になります。
なお、特定中小企業者等にしか認められていない、税額控除についても、中小企業者等に該当すれば、認められることになりました。税額控除について、取得等があった年に税額控除を全額について受けることができなかった場合には、1年間の繰越が可能です。なお、従来の制度と比較すると下記のようになります。
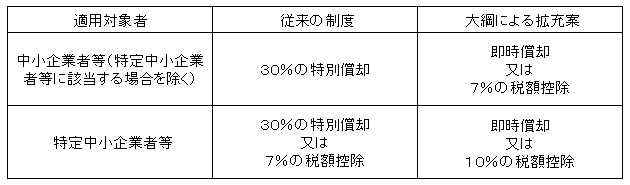
生産性向上設備投資促進税制と同様に、平成26年4月1日前に終了する事業年度で、産業競争力強化法の施行の日以後に生産性向上設備等に該当するものの取得等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度に、特別償却又は税額控除の適用を受けることになります。
少額減価償却資産の即時償却
中小企業者等が、取得価額30万円未満である減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、年間300万円を上限としてですが、その取得価額の全額について損金にできるという制度があります。
本制度については、平成26年3月31日までの時限立法となっていましたが、今回の大綱によれば2年間延長され、平成28年3月31日までの取得資産が対象となります。